連載
3D NANDフラッシュの高層化と記憶密度の推移:福田昭のストレージ通信(186) アナリストが語る不揮発性メモリの最新動向(13)(2/2 ページ)
今回は、3D NANDフラッシュ技術の高密度化をけん引してきた高層化と多値化の推移について解説する。
超高層ビルディングと化す3D NANDのメモリセルアレイ
3D NANDフラッシュの高層化はしばしば、高層ビルディングに例えられる。対するプレーナー(2D)NANDフラッシュはさしずめ、平屋あるいは低層のアパートメントだろうか。
2D NANDフラッシュの高さは、1μmに満たない。これに対して3D NANDフラッシュは24層〜32層で既に3μm前後と、大規模半導体集積回路(LSI)としては異常な高さに達していた。64層は5μm前後、72層は6μm前後とさらに高層化する。96層は7μm前後に達する。
高層化は、メモリセルを縦方向に接続する孔(「メモリスルーホール」と呼ぶ)の形成を著しく難しくする。このため、メモリスルーホールの形成を2段階で実施するプロセスが採用されている。例えば64層であれば、32層のスルーホールを2回形成する工程に分ける。

3D NANDフラッシュの高層ビルディング。配布資料では薄いアミをかけていた。出典:FMS 2020の講演「Technology Trend:NAND & Emerging Memory」の配布資料(クリックで拡大)
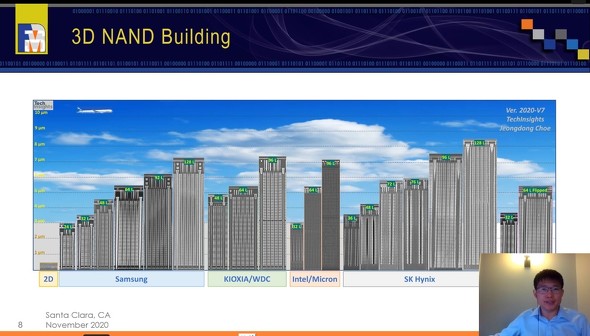
3D NANDフラッシュの高層ビルディング。講演スライドではメモリセルアレイの断面を電子顕微鏡で観察した画像を示していた。出典:FMS 2020の講演「Technology Trend:NAND & Emerging Memory」のスライド(クリックで拡大)
なおSamsungだけは、メモリスルーホールの形成を1回で済ませている。同じ積層数でも、Samsungの3D NANDはあまり高くない。特に92層と128層では、他社に比べて低い。メモリスルーホール作成の難しさを緩和していることがうかがえる。
(次回に続く)
⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 中国の3D NANDフラッシュメーカー「YMTC」の現状
中国の3D NANDフラッシュメーカー「YMTC」の現状
今回は、中国の3D NANDフラッシュベンチャーであるYMTC(Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.)の現状に関する講演部分を紹介する。 高層化の継続で、製造コストを爆下げする3D NANDフラッシュ
高層化の継続で、製造コストを爆下げする3D NANDフラッシュ
今回からは、半導体メモリのアナリストであるMark Webb氏の「Flash Memory Technologies and Costs Through 2025(フラッシュメモリの技術とコストを2025年まで展望する)」と題する講演の概要をご紹介する。 ソニーが20年度通期業績を上方修正、CMOSセンサーも想定上回る
ソニーが20年度通期業績を上方修正、CMOSセンサーも想定上回る
ソニーは2021年2月3日、2021年3月期(2020年度)第3四半期(2020年10〜12月期)決算を発表するとともに、2020年度通期業績予想を上方修正した。 前進し続けるIntel
前進し続けるIntel
Intelは2021年1月21日(米国時間)、業績発表を行った。それを見ると、同社の“終末時計”のカウントダウンに、少なくとも数秒は追加されたといえるだろう。ただし、完全に楽観視できるわけではなさそうだ。スピンドクター(情報操作が得意な人)たちは、Intelの2020年の業績のマイナス面だけを簡単に強調することができる。また、プラス面よりも欠点の方に反応を示す投資家たちもいる。 HDD大手Western Digitalの業績、前年同期比の営業利益が3四半期連続で増加
HDD大手Western Digitalの業績、前年同期比の営業利益が3四半期連続で増加
今回は、米Western Digitalの2021会計年度第1四半期の業績を紹介する。 新材料で次々世代を狙う「強誘電体メモリ(FeRAM)」
新材料で次々世代を狙う「強誘電体メモリ(FeRAM)」
今回は「強誘電体メモリ(FeRAM)」を取り上げる。FeRAMの記憶原理と、60年以上に及ぶ開発の歴史を紹介しよう。