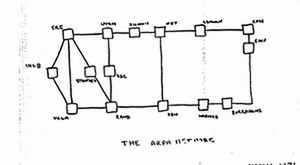インターネット時代の幕開け:イノベーションは日本を救うのか 〜シリコンバレー最前線に見るヒント〜(5)(2/2 ページ)
今回は、シリコンバレーの発展に欠かせない要素であるPCとインターネットの歴史について、触れてみたい。これら2つは、シリコンバレーだけでなく世界を大きく変えることになった。
イーサネットの登場
1980年に入ると今度はPCやワークステーションなどをより効率よく使うためのソフトウェア企業が数多く生まれるようになった。マイクロソフトのDOS(Disk Operating System)や表計算のビジカルク(VisiCalc)が出てきたのも、このころである。
1980年代半ばになると、今度はこれらのPC、ワークステーション、コンピュータをつなぐための通信技術が、次の波としてシリコンバレーに押し寄せた。
PARCに在籍していたボブ・メトカーフがイーサネットを発明したのは1973年のことだ。その後メトカーフは1979年、3Com(スリーコム)という会社を設立した。1980年代の半ば、先述した通り、コンピュータ同士を接続したいというニーズが爆発的に高まったことでイーサネットはLANのスタンダードになった。
そして1984年、互換性のないコンピュータ同士をつなげるルーターを開発するためにシスコ・システムズが創立された。
インターネットの商業化が進む
1990年代になると、遠隔地のコンピュータをネットワークでつなぐインターネットの商業化が始まった。
インターネットの起源はアルパネット(ARPANET:Advanced Research Projects Agency Network)と呼ばれ、1960年代末の冷戦のさなかに、米国国防省の傘下にある米国防高等研究計画局(DARPA)が中心となって開発されたネットワークであることは、よく知られている。なお、ARPANETは1985年にInternet(インターネット)という名称に変わった。
当時、インターネットブラウザなどは存在しない。ARPANETは、政府や大学の関係者が、もっぱら電子メールを利用するためだけに使われていた。通信速度は約150ビット/秒(bps)、最大でも300bps程度で、1秒間に40文字も送れないような時代だったのである。
同じころ、データ通信を行う機器として「音響カプラ」が使われていた。データを音声信号に変換し、電話の受話器を介してデータを送受信する、いわばモデムである。若い世代の皆さんは知らないと思うので、ぜひ検索してみてほしい。右の画像のように、電話機の受話器をカパッとはめている面白い機器の写真がたくさん見つかるはずだ。
1993年には、モザイク・コミュニケーションズが、初のインターネットブラウザ「NCSA Mosaic」をリリースし、インターネット時代の幕開けを飾った。Mosaicは、米国イリノイ大学のスーパーコンピュータ応用研究所(NCSA:National Center for Supercomputing Applications)のマーク・アンドリーセンが中心となって開発したものだ。モザイク・コミュニケーションズは、アンドリーセンが、シリコングラフィックスの創立者でスタンフォード大学の教授でもあったジム・クラークとともに立ち上げた会社で、後のネットスケープコミュニケーションズである。
1990年代の半ば、インターネットが普及し始めると、インターネット・インフラをベースにした、さまざまなビジネスチャンスが大きく広がってきた。IT技術が生産性に及ぼす影響が大きな分野は、ニュー・エコノミーとして脚光を浴びるようになった。これらインターネット関連の新しいソフトウェアや、インターネット・インフラを支える新しいハードウェアも多く開発されるようになった。インターネットの商業化は、世界中の情報産業のみならず、経済活動や人々の日常生活まで変えてしまったといっても過言ではないだろう。
こうした始まったインターネットバブルは、2000年代に向けて猛進していくのである。
(次回につづく)
⇒「イノベーションは日本を救うのか 〜シリコンバレー最前線に見るヒント〜」連載バックナンバー
Profile
石井正純(いしい まさずみ)
ハイテク分野での新規事業育成を目標とした、コンサルティング会社AZCA, Inc.(米国カリフォルニア州メンローパーク)社長。
米国ベンチャー企業の日本市場参入、日本企業の米国市場参入および米国ハイテクベンチャーとの戦略的提携による新規事業開拓など、東西両国の事業展開の掛け橋として活躍。
AZCA, Inc.を主宰する一方、ベンチャーキャピタリストとしても活動。現在はAZCA Venture PartnersのManaging Directorとして医療機器・ヘルスケア分野に特化したベンチャー投資を行っている。2005年より静岡大学大学院客員教授、2012年より早稲田大学大学院ビジネススクール客員教授。2006年よりXerox PARCのSenior Executive Advisorを兼任。北加日本商工会議所、Japan Society of Northern Californiaの理事。文部科学省大学発新産業創出拠点プロジェクト(START)推進委員会などのメンバーであり、NEDOの研究開発型ベンチャー支援事業(STS)にも認定VCなどとして参画している。
新聞、雑誌での論文発表および日米各種会議、大学などでの講演多数。共著に「マッキンゼー成熟期の差別化戦略」「Venture Capital Best Practices」「感性を活かす」など。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 日本半導体産業の立役者! 「電卓」の奥深い世界
日本半導体産業の立役者! 「電卓」の奥深い世界
“最も身近な精密機器”と言っても過言ではない電卓。あまり一般には知られていないが、電卓は、PCの誕生や日本の半導体産業の発展を語る上で欠かせない存在だ。3月20日の「電卓の日」に、奥深い電卓の世界をのぞいてみたい。 Intelの10nmチップ、鍵はIII-V族半導体と量子井戸構造か
Intelの10nmチップ、鍵はIII-V族半導体と量子井戸構造か
Intelは10年近くにわたり、量子井戸電界効果トランジスタ(QWFET)の研究を進めてきた。ある半導体アナリストは、Intelの10nmチップは、III-V族半導体、具体的にはInGaAs(インジウム・ガリウム・ヒ素)とGe(ゲルマニウム)を用いたQWFETになると予測している。 EtherCAT通信の仕組みを知ろう〜メイドは超一流のスナイパー!?
EtherCAT通信の仕組みを知ろう〜メイドは超一流のスナイパー!?
今回は、EtherCATの仕組みを信号レベルでご説明します。「ご主人様(EtherCATマスタ)」と「メイド(EtherCATスレーブ)たち」が、何をどのようにやり取りをしているのかを見てみると、「メイドたち」が某有名マンガのスナイパーも腰を抜かすほどの“射撃技術”を持っていることが分かります。後半では、SOEM(Simple Open EtherCAT Master)を使ったEtherCATマスタの作り方と、簡単なEtherCATの動作チェックの方法を紹介しましょう。 TV事業に固執し続ける日本メーカー
TV事業に固執し続ける日本メーカー
日本国内のTV出荷台数は大幅に減少しているにもかかわらず、いつまでもTV事業に固執し続ける日本の電機メーカー。オリンピックなどの世界的な祭典に期待をかける傾向があるようだ。 5Gでは周波数帯で世界的な協調が必要に
5Gでは周波数帯で世界的な協調が必要に
Ericssonは、モバイル通信市場を包括的に分析したレポート「エリクソン・モビリティ・レポート」を年に2回発行している。同社の日本法人であるエリクソン・ジャパンは2016年7月5日、同レポートの最新版となる2016年6月版の内容を説明する記者発表会を行った。モバイル通信市場の最新動向に加え、3GPPによる5G(第5世代)標準化活動のアップデートについても説明した。 ソニーは再び輝けるか、復活支える名機と一流技術(前編)
ソニーは再び輝けるか、復活支える名機と一流技術(前編)
最近は赤字や経営難ばかりが取り沙汰されているソニー。オーディオや映像、ゲームなどの分野で数々の大ヒット製品を生み出してきた輝かしい歴史は、忘れ去られているようにすら感じる。だが同社の製品ポートフォリオを詳しく調べてみれば、市場をけん引してきた名機や一流技術の存在に、あらためて気づくはずだ。