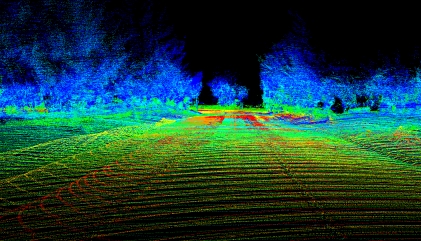自動運転向けライダー技術、競争激化の気配:市場をけん引するVelodyneを追う企業が続々
ライダー(レーザーレーダー)が自動運転車に求められるセンサー技術の1つとして浮上する中、ライダーを専門とする新興企業が、イスラエル、ドイツ、カナダ、米国ニューメキシコ州やカリフォルニア州のあちこちに出現している。
ライダー市場をけん引するVelodyne
2007年に初めて製品を出荷した米Velodyne Lidar(以下、Velodyne)は、今も圧倒的な実績と資金力を持つライダー技術企業であり続けている。同社が2016年8月16日(現地時間)に発表したところによると、Ford Motor(以下、Ford)と中国の大手サーチエンジン企業Baiduは共同で1億5000万米ドルをVelodyneに出資するという。
Velodyneは現在、同社のライダーイメージングユニット「VLP 16」と「VLP 32」をベースにしたものを含む、複数の新製品ラインをサンプル出荷している。同社のプレジデント兼最高執行責任者(COO)であるMike Jellen氏は、守秘義務契約を理由にデザインウィンについて明確に述べることはなかったが、Velodyneのライダー技術が既に25件の自動運転プログラムに用いられていることを明らかにした。
Linley Groupでシニアアナリストを務めるMike Demler氏は、EE Timesに対し、「Velodyneは、事実上全ての自動車メーカーとティア1サプライヤーが同社製のライダーセンサーを採用していると主張している」と語った。
報道によると、Baidu、Ford、Google、日産自動車、Volvoは、自動運転車の試験車にVelodyneの製品が採用されているという。また、フランスのNavya Armaなども、自動運転車にVelodyneの製品を用いている。Navya Armaは、自動運転の電気自動車を製造しているメーカーだ。
新興企業が次々に登場
とはいえ、自動車業界において、自動運転車は黎明(れいめい)期にある。新興企業が次々に設立されることに伴い、より低コストかつ小型のライダーについて既に競争が起こっている。この競争は、Velodyne以外の企業がVelodyneを追う構図となっている。そのような企業の例として、そのような企業の例として、米Quanergy Systems(以下、Quanergy)、イスラエルInnoviz Technologies、米Aerostar、カナダLeddarTech、カナダPhantom Intelligence、米Strobe、米TriLumina、ドイツIbeo Automotive Systemsが挙げられる。
「2016 International CES」(2016年1月6〜9日、米ラスベガス)で、2016年のConsumer Electronics Show(CES)で自動走行車向けソリッドステート型ライダーを発表したQuanergyは、センサー1台当たりのコストを250米ドルまで大幅に下げる計画を協議していた。同社は2015年秋、Delphi Automotive Systemsとライダー開発で提携することを発表したが、その製品はまだ発売に至っていない。
Strategy Analyticsでグローバルオートモーティブプラクティス担当ディレクタを務めるIan Riches氏は、「Quanergyは量産車のデザインウィンについて公式には何も明らかにしていないが、同社にはMercedes Benz、Hyundai、Renault-Nissanなどの“パブリックパートナー”がいる」と記した。
Riches氏は、VelodyneとQuanergyのライダーの違いについて、「決定的な違いは、Velodyneのライダーはソリッドステートハイブリッドである点だ。作動や検知はソリッドステートだが、スキャニングは機械式だということになる。一方、Quanergyのライダーは完全にソリッドステートであり、可動部品は用いられていない」と説明した。
【翻訳:青山麻由子、編集:EE Times Japan】
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 “人の目を超える”、UWBを使った3Dセンサー
“人の目を超える”、UWBを使った3Dセンサー
イスラエルのVayyar Imagingが開発した「3Dセンサー技術」は、超広帯域(UWB:Ultra Wide Band)無線周波数を利用して、対象物を画像化するものだ。乳がんの検査用に開発されたこの技術は、ガス管の検査からセキュリティチェック、高齢者の見守り、食品の組成検査まで幅広い分野に応用できる可能性がある。 自動運転車に関する3つの疑問
自動運転車に関する3つの疑問
自動運転技術への関心は、日増しに高まっている。だが、“技術的に可能なこと”が、“本当に必要なこと”とは限らない。 自動運転技術、未完のまま市場に出る恐れも
自動運転技術、未完のまま市場に出る恐れも
自動運転車への注目度が日に日に高まっている。生命に直接関わる技術なだけに課題は山積だが、市場拡大が急ピッチで進んでいることから、自動運転技術が成熟する前に、自動運転車が市場に投入されてしまうのではないか、と懸念する声もある。 ルネサスが“クルマ”を売る!? その真意とは
ルネサスが“クルマ”を売る!? その真意とは
ルネサス エレクトロニクスは米国で開催した「DevCon 2015」で、同社のADAS(先進運転支援システム)向けの最新SoCなどを搭載した自動車を披露した。実は、この自動車は、自動運転車などの開発を促進すべく同社が発表した“プラットフォーム”である。 クルマの厳しい要求仕様に応えるDRAMとフラッシュメモリ
クルマの厳しい要求仕様に応えるDRAMとフラッシュメモリ
今回は、自動車のエレクトロニクスシステム、具体的には、ADAS(先進運転支援システム)およびクラスタ・ダッシュボード、車載インフォテインメントで使われるメモリを解説する。さらに、これらのメモリの5年後のロードマップも見ていこう。 幽霊や極低温原子、FPGAを手軽に使って処理
幽霊や極低温原子、FPGAを手軽に使って処理
大量のデータから目的の情報を得る、極めて複雑な設定条件から正しい組み合わせを見つける。ミリ波レーダーや量子コンピュータの開発課題だ。National Instruments(NI)の年次カンファレンス「NIWeek 2016」(テキサス州オースチン)では、このような開発事例を3日目の基調講演において複数紹介した。