最大63%の変換効率を備える新型太陽電池構造:発電コスト7円/kWh達成へ
神戸大学の研究グループが、理論予測上の変換効率が最大63%に及ぶ新型の太陽電池セル構造を開発した。経産省が目標とする2030年の発電コスト7円/kWhを達成するには、太陽電池の変換効率を50%以上に引き上げる必要があるが、この太陽電池セル構造はその条件を十分に満たす。
2030年の発電コスト目標7円/kWh実現か
神戸大学は2017年4月7日、同大学工学研究科電気電子工学専攻の喜多隆教授と朝日重雄特命助教らの研究グループが、理論予測上の変換効率が最大63%に及ぶ新型の太陽電池セル構造を開発したと発表した。この太陽電池セル構造は、これまで太陽電池セルを透過し損失となっていたエネルギーの吸収が可能で、発電コストの大幅な削減に道を開く可能性がある。
太陽電池の変換効率が50%を超えると、経産省が目標とする2030年の発電コスト7円/kWhは達成できる。だが、従来の単接合太陽電池は約30%が理論的な限界だ。現時点の変換効率の世界記録は4接合太陽電池によるものだが、それでも46%である。
これまでの太陽電池には、入射する太陽光エネルギーの大半が吸収されずに透過したり、光子の余剰エネルギーが熱になったりと、まだ十分にエネルギーを活用できていないところがある。こうした大きな損失を抑制することが、発電コストの削減には不可欠だ。
そこで研究グループは今回、異なるバンドギャップの半導体からなるヘテロ界面を利用した太陽電池を透過するエネルギーの小さな2つの光子を用い、光電流を生成する太陽電池セル構造を開発した。この太陽電池セル構造は、かつて損失となっていた波長の長い太陽光のスペクトル成分を吸収でき、変換効率最大63%という理論予測結果を示す。
今回の研究では、この太陽電池セル構造のユニークなメカニズムである2光子によるアップコンバージョン(エネルギー昇圧)の実験実証にも成功。実証された損失抑制効果は、従来の中間バンドを利用した方法に比べて100倍以上にも達した。研究グループは今後、最適な材料を利用した太陽電池セル構造の設計や変換効率にかかる性能評価を進めるとしている。
関連記事
 日本企業が世界最高水準、記録的な発電コスト
日本企業が世界最高水準、記録的な発電コスト
太陽電池を用いた発電方式が化石燃料に取って替わるかどうか。1枚の太陽電池の発電コストを決めるのは、変換効率と寿命、製造コストだ。だが、太陽電池を大量に利用した大規模な発電所を作り上げる際には、他の要因がより効いてくる。アラブ首長国連邦アブダビに建設を予定する太陽光発電所の事例から、順調に発電コストが下がっていることが分かる。 CIS系薄膜太陽電池で、19.2%の変換効率達成
CIS系薄膜太陽電池で、19.2%の変換効率達成
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)とソーラーフロンティアは、外形寸法が30×30cmのCIS系薄膜太陽電池サブモジュールを開発し、変換効率19.2%を達成した。 太陽電池の効率を66%まで高める手法、“量子影状態”の発見で可能性が開く
太陽電池の効率を66%まで高める手法、“量子影状態”の発見で可能性が開く
自然エネルギーを利用した発電の注目度が高まる中、米大学の研究チームが太陽光を効率良く電気エネルギーに変換する新たな手法を発表した。太陽電池の変換効率を、従来の2倍に高められる可能性を秘めているという。 シリコン用いた太陽電池、「限界」突破するには
シリコン用いた太陽電池、「限界」突破するには
EE Times Japanに掲載した記事を読みやすいPDF形式の電子ブックレットに再編集した「エンジニア電子ブックレット」。今回は、米NRELとスイスCSEMが2016年1月に発表した29.8%という高い変換効率を得ている太陽電池に関するインタビューを紹介します。 カネカ、太陽電池モジュールで変換効率24.37%達成
カネカ、太陽電池モジュールで変換効率24.37%達成
カネカは、結晶シリコン太陽電池モジュールで「世界最高」となる変換効率24.37%を達成したと発表した。2020年の14円/kWhという発電コスト目標の達成に向けて大きく前進したという。 ペロブスカイト太陽電池、世界最高級の変換効率
ペロブスカイト太陽電池、世界最高級の変換効率
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と物質・材料研究機構(NIMS)の研究チームは、1cm角のペロブスカイト太陽電池セルで、エネルギー変換効率18%超を達成した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング

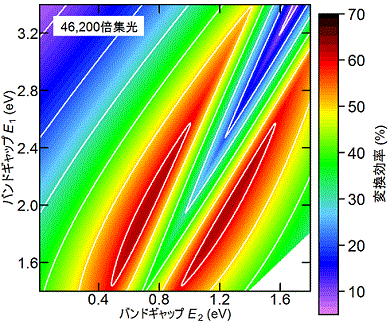 変換効率の理論予測。ヘテロ界面を形成する2つの異なるバンドギャップの変化に応じて効率が変化する。最大変換効率は63%。
変換効率の理論予測。ヘテロ界面を形成する2つの異なるバンドギャップの変化に応じて効率が変化する。最大変換効率は63%。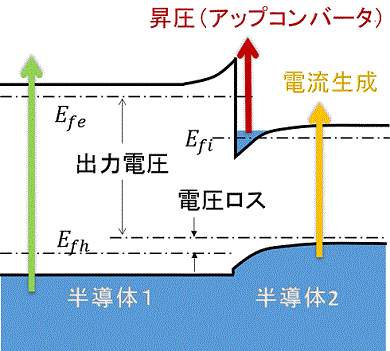 ヘテロ界面を利用した太陽電池構造と2光子(図中の黄色と赤の矢印)のアップコンバージョンの様子。半導体1だけだと本来は透過するような赤矢印や黄色矢印の光が吸収されて電流を大幅に増加させる。
ヘテロ界面を利用した太陽電池構造と2光子(図中の黄色と赤の矢印)のアップコンバージョンの様子。半導体1だけだと本来は透過するような赤矢印や黄色矢印の光が吸収されて電流を大幅に増加させる。