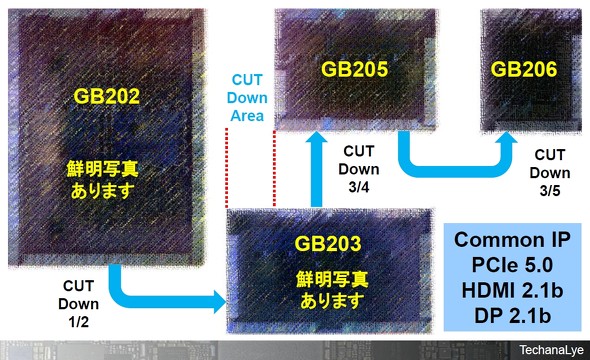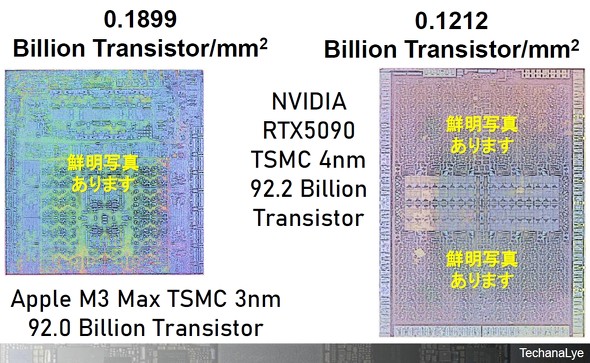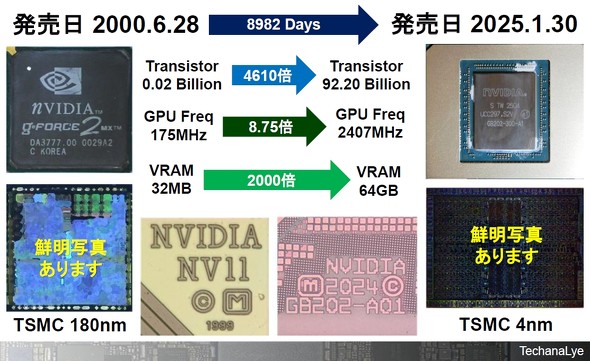2025年は数年に一度の「ビッグチェンジ」イヤー、NVIDIAとAMDの最新GPUを分解:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(94)(3/4 ページ)
4つのシリコンを比較する
図5はエントリーのRTX 5050 GB207を除くNVIDIA Blackwellの4シリコンの様子である。カットダウンで構成されるスケーラブルシリコンになっている。演算器コア数やキャッシュメモリとともに、VRAMインタフェースのチャンネル数もカットダウンされている。個々のコア、PHYは同じものを活用し、スケールの変更でバージョンを作り上げているわけだ。スケール化することでテストパターンなどが流用できる利点なども大きい。一番大きなシリコンであるRTX 5090 GB202が設計難易度は一番高い。搭載トランジスタが多く、電源ドロップ、ノイズ対策、クロックスキュー調整などの課題は面積に比例して増える。一番難易度の高いものを先に設計して、それをベースにしてカットダウンすることがもっとも合理的だ(一般的に大きいチップほど電源ドロップも大きく、クロックスキュー合わせなどが難しいので製品周波数も大きいチップが若干低い)。
図6は現在市販される最大トランジスタ搭載チップ2件の様子である。ともに920億トランジスタ超え。製造プロセスが異なるので同軸比較にはならないが、ともに1平方ミリメートル当たり1億トランジスタを超えている。スマートフォン向けでは、既に1平方ミリメートル当たり2億トランジスタ超えチップも出回っており、今後2nm世代、1.4nm世代のプロセスなどで3億超えを見る日も近いだろう。
25年前のチップと比較してみる
図7は25年前のNVIDIA「NV11(開発コードネーム)」と最新のRTX 5090の比較である。さまざまな数字が数千倍となっている。四半世紀の進化が目に見える数字となっているわけだ(あらためて感慨深い!)。今後もややペースは落ちるもののイノベーテッドな数字を見続けることができそうなので、日々努力を重ねている製造や設計開発メーカー、エンジニアに敬意を示したい。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加
- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損
- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす
- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却