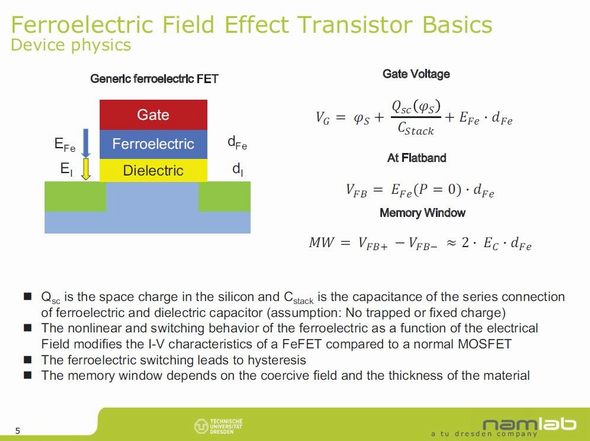究極の高密度不揮発性メモリを狙う強誘電体トランジスタ:福田昭のストレージ通信(73) 強誘電体メモリの再発見(17)(2/2 ページ)
» 2017年09月05日 10時30分 公開
[福田昭,EE Times Japan]
メモリ特性とスイッチング特性の両方を考慮
「FeFET(Ferroelectric FET)」あるいは「強誘電体トランジスタ」の基本的な構造は、かなりシンプルである。シリコン基板(シリコンウエハー)の表面には、常誘電体の薄いゲート絶縁膜が載る。その上に、強誘電体の絶縁膜が載り、最上層はゲート電極となる。普通のMOSFETとの違いは、ゲート絶縁膜が2層構造になっただけ、ともいえる。
ただしトランジスタの設計はかなり複雑だ。普通のMOSFETはスイッチあるいはアンプであり、メモリではない。しかし強誘電体トランジスタはメモリなので、スイッチング特性とメモリ特性の両方が関連する。ゲート電圧、ドレイン電流、ゲートスタックの静電容量、常誘電体膜中の電界、強誘電体膜中の電界、強誘電体のスイッチング特性(分極反転特性)、強誘電体の膜厚と抗電界などを考慮しなければならない。
例えばメモリウィンドウ(オン状態とオフ状態の差分)は、強誘電体の膜厚と抗電界の大きさに比例する。また書き込みの速度は、スイッチング特性(分極特性)に依存する。
強誘電体トランジスタ(FeFET)の研究は、従来の強誘電体材料であるペロブスカイト系セラミックスと、強誘電性の有機高分子を使い、1990年代後半から活発になってきた。次回は、その歩みをご報告しよう。
(次回に続く)
⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧
関連記事
 PCIeが今後の主流に
PCIeが今後の主流に
今回から始まるシリーズでは、SSDインタフェースの最新動向に焦点を当てて解説する。SSD関連のインタフェースは数多く存在するが、近年、採用が進んでいるのがPCIeだ。 NVIDIAがエネルギー効率の高い相互接続技術を解説(前編)
NVIDIAがエネルギー効率の高い相互接続技術を解説(前編)
バスやリンクなどの相互接続(インターコネクト)は大きなエネルギーを消費する。では、どのようにして消費電力を下げ、エネルギー効率を高めればよいのか。前編では、信号振幅を小さくする方法と、電荷を再利用する方法の2つについて解説する。 メモリ価格の高騰はしばらく続く
メモリ価格の高騰はしばらく続く
DRAMとNAND型フラッシュメモリは価格は上昇していて、この傾向は今後もしばらく続くという。 東芝メモリの売却先はまだ決まらず
東芝メモリの売却先はまだ決まらず
東芝は、東芝メモリについて「2017年8月31日の取締役会で売却先を決定」とする一部の報道を否定し、「開示すべき決定事項はない」として、売却先がまだ決定していないことを明らかにした。 東芝がQLCの3D NANDを試作、96層プロセスの開発も
東芝がQLCの3D NANDを試作、96層プロセスの開発も
東芝メモリは、同社の3D NAND型フラッシュメモリ「BiCS FLASH」について、4ビット/セル(QLC)技術を用いた試作品と、96層積層プロセスを用いた試作品を開発し、基本性能を確認したと発表した。 2017年の世界半導体市場、WSTSが上方修正
2017年の世界半導体市場、WSTSが上方修正
世界半導体市場統計(WSTS)は、2017年第2四半期の半導体市場の実績値に基づき、2017年の同市場の予測を更新した。2016年比で11.5%増としていた見通しを、17%増に上方修正している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special ContentsPR
特別協賛PR
スポンサーからのお知らせPR
Special ContentsPR
Pickup ContentsPR
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす
- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加
- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか
Special SitePR
あなたにおすすめの記事PR