富士通三重工場の売却も決定……これからどうなる? 日本の半導体工場:大山聡の業界スコープ(7)(2/3 ページ)
「製造」に重点が置かれた日本の半導体産業
日系各社の半導体事業は、規模にバラツキはあるが、いずれも50年前後の長い歴史を持っている。自社内に必要な半導体を自力で開発し、自力で製造する、という企業がそれだけ存在していたことの証でもあるわけだが、半導体事業を社内の一部門として居続けさせるには、技術進化も市況変化も激し過ぎて流れに適応させることが難しい、という現実も物語っている。
この点を少々補足すると、半導体の流通が今ほど活性化していなかった当時は、半導体を使いたければ自ら作るしかなかった、というのが各社における半導体事業発足の経緯である。すでに存在する社内ニーズに対応することが最優先で、どんな半導体を開発すべきか、どこに売りに行くべきか、といった議論は二の次。その後、プロセス技術が蓄積してきた大手電機メーカー各社は、外販用にDRAMの製造も始めるが、これも製品コンセプトやアプリケーションが非常に明確な製品であり、「作れば売れる」と信じた各社が事業を拡大してきた。一般に製造業は、「開発」「製造」「販売」が三位一体となる必要があるが、製品化の対象が明確であった日本の半導体産業では「製造」に大きな重点が置かれ、「どれだけ作れるか」を各社が競い合いながら推移してきたのが実態である。
ところが、米国を中心にファブレスメーカーが、韓国を中心にメモリメーカーが台頭し始めると、日系各社の立ち位置が危うくなり始める。焦った日系各社は、ここで大きな間違いを犯してしまったのである。
日本半導体産業衰退の始まりは、システムLSIへのシフト
日系各社は、DRAMコスト競争で韓国勢および米国勢に勝てなくなり、半導体事業の戦略をメモリ中心からシステムLSI中心へと切り替えた。当時は「賢明な判断」「それが必然」と周囲からも評価されていたが、実はこれが日本半導体産業衰退の始まりであった。
日系各社としては、これ以上メモリ事業を継続しても収益改善のメドが立たない、しかし工場を閉鎖したくないので、システムLSIを早く立ち上げて量産するしかない、と判断した。だが、システムLSIとはどのような半導体か、どのような戦略でどのアプリケーションに売り込むのか、という具体的な戦略が立案できていなかったのだ。
「戦略商品はシステムLSI、狙う市場はユビキタス」などという説明も何度か聞かされたが、具体的なイメージを伴っていたわけではない。そもそも「ユビキタス」という言葉は、いつでもどこでもネットに接続できる、という概念を総称する単語だったが、この概念を具体化した商品であるスマートフォンが普及した現在、「ユビキタス」という単語は使われなくなった。では、日系メーカーはスマートフォンにシステムLSIを売り込めたのか。残念ながら成功事例は皆無だ。そもそもシステムLSIで利益を稼いでいる日系企業など存在しない。この実体のない言葉を使用する限り、具体的な戦略立案も難しいのではないだろうか。
多くの場合、システムLSIはハイエンドのロジックICを指しており、米国系を中心としたファブレスメーカーが上位を占めている。つまり、システムLSIで成功している企業の多くはファブレスで、設計に専念することで製造を外部に委託するスタンスを保っている。工場の稼働を維持するためにこれを立ち上げようとした日系各社とは、根本的に戦略が違うのだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング

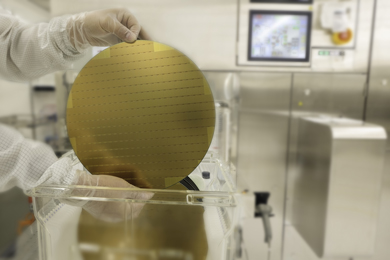 画像はイメージです
画像はイメージです