EE Times Japan >
LSI >
多層配線のビア抵抗を大幅に低減する「スーパービア」:福田昭のデバイス通信(322) imecが語る3nm以降のCMOS技術(25)(2/2 ページ)
» 2021年09月16日 11時30分 公開
[福田昭,EE Times Japan]
2層分の配線間を一気に貫通する「スーパービア」
そこで考案されたのが、M3からM1を一気に貫通するビア「スーパービア(supervia)」である。製造工程は、例えば以下のようになる。M1とM2(あるいはダミーのM2)を形成し、M2の上に層間絶縁膜を成膜する。その上に窒化チタン(TiN)のハードマスクを堆積し、M1の表面まで貫通する垂直な孔(スーパービア)を掘る。それからスーパービアに高融点金属(例えばルテニウム(Ru))を埋め込むとともに、M3を成膜する。
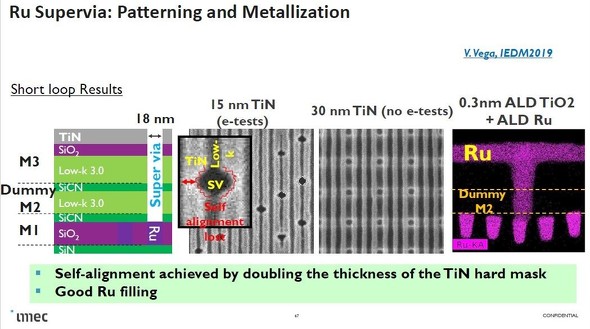 第3層金属配線(M3)と第1層金属配線(M1)を接続するスーパービアの製造工程。左端は構造図。M2はダミー層である。右端はM3を形成後の断面を、エネルギー分散型X線分光分析装置(EDS装置)と電子顕微鏡で観察した画像。中央の写真2点はハードマスク(TiN)層の厚みによるビアパターンの違い。TiN層を30nmと厚くすることで、良好なパターンを得られる。出典:imec(IEDM2020のチュートリアル講演「Innovative technology elements to enable CMOS scaling in 3nm and beyond - device architectures, parasitics and materials」の配布資料) (クリックで拡大)
第3層金属配線(M3)と第1層金属配線(M1)を接続するスーパービアの製造工程。左端は構造図。M2はダミー層である。右端はM3を形成後の断面を、エネルギー分散型X線分光分析装置(EDS装置)と電子顕微鏡で観察した画像。中央の写真2点はハードマスク(TiN)層の厚みによるビアパターンの違い。TiN層を30nmと厚くすることで、良好なパターンを得られる。出典:imec(IEDM2020のチュートリアル講演「Innovative technology elements to enable CMOS scaling in 3nm and beyond - device architectures, parasitics and materials」の配布資料) (クリックで拡大)imecは、銅(Cu)とコバルト(Co)、ルテニウム(Ru)でそれぞれ、M1とM3を接続するスーパービアを試作してみた。銅(Cu)はビア底部内壁への埋め込みが不十分であり、コバルト(Co)はビア電極内部にボイド(空孔)が生じた。良好にビア電極とM3を形成できたのは、ルテニウム(Ru)だけだった。
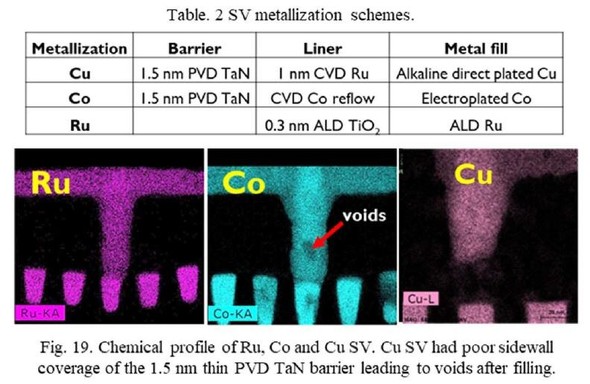 銅(Cu)とコバルト(Co)、ルテニウム(Ru)でそれぞれ、M1とM3を接続するスーパービアを試作した結果。上の表はバリアとライナー、配線の金属と成膜方法。下の写真はEDS装置と電子顕微鏡を併用して観察した断面画像。出典:imec(IEDM 2019の発表論文「Three-Layer BEOL Process Integration with Supervia and Self-Aligned-Block Options for the 3nm node」(論文番号19.3)) (クリックで拡大)
銅(Cu)とコバルト(Co)、ルテニウム(Ru)でそれぞれ、M1とM3を接続するスーパービアを試作した結果。上の表はバリアとライナー、配線の金属と成膜方法。下の写真はEDS装置と電子顕微鏡を併用して観察した断面画像。出典:imec(IEDM 2019の発表論文「Three-Layer BEOL Process Integration with Supervia and Self-Aligned-Block Options for the 3nm node」(論文番号19.3)) (クリックで拡大)従来技術の42%にビア抵抗を大きく削減
そこでルテニウム(Ru)の多層配線で、M1とM3を接続するビアの電気抵抗を従来技術(スタックビア)とスーパービアで比べてみた。M1とM3は互いに平行な直線群で配線ピッチは36nm、M2はM1(およびM3)と直交する平行直線群で配線ピッチは21nmである。
試作したビアの抵抗値(中央値)は従来技術が66.4Ω、スーパービアが27.7Ωだった。スーパービアの抵抗値は、従来技術の2.4分の1(42%)と大幅に減少した。
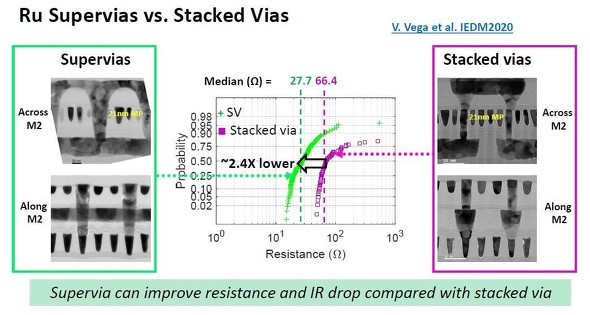 スーパービア(左)と従来技術(スタックビア)(右)の抵抗値(測定値)。写真は断面の電子顕微鏡観察像。配線ピッチはM2が21nm、M1とM3が36nm。出典:imec(IEDM2020のチュートリアル講演「Innovative technology elements to enable CMOS scaling in 3nm and beyond - device architectures, parasitics and materials」の配布資料) (クリックで拡大)
スーパービア(左)と従来技術(スタックビア)(右)の抵抗値(測定値)。写真は断面の電子顕微鏡観察像。配線ピッチはM2が21nm、M1とM3が36nm。出典:imec(IEDM2020のチュートリアル講演「Innovative technology elements to enable CMOS scaling in 3nm and beyond - device architectures, parasitics and materials」の配布資料) (クリックで拡大)(次回に続く)
⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧
関連記事
 CMOS多層配線の高密度化を支えるビア電極の微細化
CMOS多層配線の高密度化を支えるビア電極の微細化
今回は、多層配線技術の中核を成すビア電極技術について解説する。 高アスペクト比、バリアレス、エアギャップが2nm以降の配線要素技術
高アスペクト比、バリアレス、エアギャップが2nm以降の配線要素技術
今回は、銅配線からルテニウム配線への移行と微細化ロードマップについて紹介する。 埋め込みDRAMが大容量キャッシュの製造コスト低減に貢献
埋め込みDRAMが大容量キャッシュの製造コスト低減に貢献
今回はDRAMをロジックLSIに埋め込む技術「eDRAM」の製品化事例を解説する。 HDD大手SeagateとWDの2021会計年度業績、営業利益が拡大
HDD大手SeagateとWDの2021会計年度業績、営業利益が拡大
米Seagate Technologyと米Western Digitalの、2021会計年度(2021年6月期)の業績を紹介する。 HDD大手Western Digitalの業績、前年同期比の営業利益が3四半期連続で増加
HDD大手Western Digitalの業績、前年同期比の営業利益が3四半期連続で増加
今回は、米Western Digitalの2021会計年度第1四半期の業績を紹介する。 新材料で次々世代を狙う「強誘電体メモリ(FeRAM)」
新材料で次々世代を狙う「強誘電体メモリ(FeRAM)」
今回は「強誘電体メモリ(FeRAM)」を取り上げる。FeRAMの記憶原理と、60年以上に及ぶ開発の歴史を紹介しよう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special ContentsPR
特別協賛PR
スポンサーからのお知らせPR
Special ContentsPR
Pickup ContentsPR
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明
- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却
- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実
- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正
Special SitePR
あなたにおすすめの記事PR
