従来型材料を使った強誘電体トランジスタの研究開発(後編):福田昭のストレージ通信(75) 強誘電体メモリの再発見(19)(2/2 ページ)
» 2017年09月12日 11時30分 公開
[福田昭,EE Times Japan]
64kビットの不揮発性メモリを強誘電体トランジスタで試作
それから3年後の2011年9月に産総研は、強誘電体トランジスタで記憶容量が64kビットの不揮発性メモリを試作したと、報道機関向けにリリース発表した。これも、産総研の酒井滋樹氏を中心とする研究グループと、東京大学の竹内健准教授を中心とする研究グループの、共同研究成果である。
試作した不揮発性メモリの特長は、NANDフラッシュメモリと同様のメモリセルアレイ構造を採用したことだ。8個の強誘電体トランジスタをNAND接続し、1本のメモリストリングを構成した。強誘電体トランジスタの構造は、2008年5月に発表したものと基本的には変わらない。トランジスタのゲート長とゲート幅はともに5μmである。
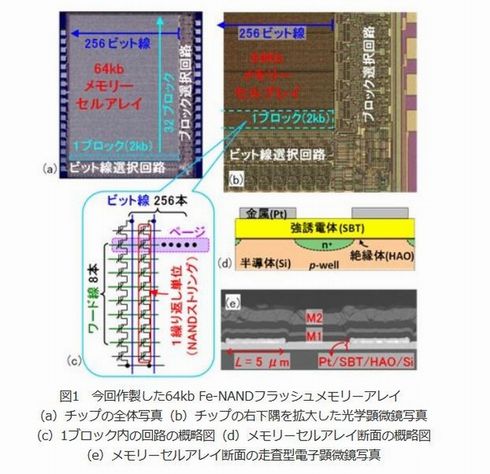 産総研と東京大学が共同開発した64kビットの強誘電体不揮発性メモリ。NAND構造の強誘電体トランジスタ(FeFET)をメモリセルに採用した。出典:産業技術総合研究所(参考リリース) (クリックで拡大)
産総研と東京大学が共同開発した64kビットの強誘電体不揮発性メモリ。NAND構造の強誘電体トランジスタ(FeFET)をメモリセルに採用した。出典:産業技術総合研究所(参考リリース) (クリックで拡大)試作した64kビットのメモリセルアレイの不良率は29.6%である。2kビットずつのブロックレベルでは、不良率は19%だった。正常に動作するメモリセルを対象に2kビットのブロックでデータ保持特性をテストしたところ、2日間のデータ保持期間を確認できた。なおデータ書き込みに必要な電圧はワード線が6V、ビット線が1Vである。
残念ながら、強誘電体トランジスタを使った不揮発性メモリは現在のところ、製品とはなっていない。今後の発展に期待したい。
(次回に続く)
⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧
関連記事
 新材料「二酸化ハフニウム」を使った強誘電体メモリへの長い道
新材料「二酸化ハフニウム」を使った強誘電体メモリへの長い道
今回から2回にわたり、強誘電体の二酸化ハフニウムが、不揮発性メモリ用のキャパシターとしてどのような特性を示しているかを解説する。強誘電体不揮発性メモリ(FeRAM)のメモリセルで重要なのは、強誘電体キャパシターの特性だ。二酸化ハフニウムを絶縁膜とする強誘電体キャパシターが、優れた特性を備えているかどうかを調べる必要がある。 FeRAMのメモリセル構造の基礎
FeRAMのメモリセル構造の基礎
強誘電体不揮発性メモリ(FeRAM)の構造には、2T2C方式、1T1C方式、チェインセル方式がある。それぞれの特徴を紹介するとともに、メモリセルの断面構造についても解説しよう。 東芝、岩手県北上市にメモリ新工場建設へ
東芝、岩手県北上市にメモリ新工場建設へ
東芝は2017年9月6日、NAND型フラッシュメモリの新製造拠点を岩手県北上市に建設する予定であると発表した。 大型パネルで大量のパッケージを一括組み立てする「FOPLP」技術
大型パネルで大量のパッケージを一括組み立てする「FOPLP」技術
前回説明したウエハーレベルのファンアウトパッケージング技術「FOWLP(Fan Out Wafer Level Packaging)」における一括製造の考え方を、パネル状の基板に適用したのが、パネルレベルのファンアウトパッケージング技術「FOPLP(Fan-Out Panel Level Packaging)」だ。今回は、FOPLPの強みや、どんなパッケージングに適しているかなどを説明する。 シリコンインターポーザを導入した高性能パッケージの製品例
シリコンインターポーザを導入した高性能パッケージの製品例
シリコンインターポーザを導入したパッケージの製品化時期は、おおむね、2012年の第1期と、2015〜2016年の第2期に分けられる。それぞれの時期を代表する製品例と、それらの特徴を紹介する。 投資ファンドによるLattice買収、破談が濃厚に
投資ファンドによるLattice買収、破談が濃厚に
未公開株式投資ファンドCanyon Bridge Capital Partnersによる、米FPGAメーカーのLattice Semiconductor(ラティス・セミコンダクター)の買収が、破談になる可能性が高まった。米国の外国投資委員会(CFIUS)が、米大統領に、本案件を中止または禁止するよう勧告したという。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special ContentsPR
特別協賛PR
スポンサーからのお知らせPR
Special ContentsPR
Pickup ContentsPR
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす
- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加
- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか
Special SitePR
あなたにおすすめの記事PR
