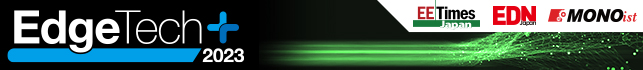Rubyで島根を町おこし 軽量言語「mruby/c」組み込み活用事例を紹介:Ruby開発者は松江市在住
しまねソフト研究開発センター(通称ITOC)は「EdgeTech+ 2025」に出展し、Rubyを中核にしたIT産業振興、地域活性化の取り組みや、組み込み・IoTデバイス向け開発言語「mruby/c」の利活用事例などを紹介した。
Rubyを中核にした「IT町おこし」
しまねソフト研究開発センター(Shimane IT Open-Innovation Center、通称ITOC)は「EdgeTech+ 2025」(2025年11月19〜21日、パシフィコ横浜)に出展し、組み込み・IoTデバイス向け開発言語「mruby/c」の利活用事例などを紹介した。
Rubyは、まつもとゆきひろ氏によって開発された、オープンソースのプログラミング言語だ。まつもと氏が島根県松江市在住であることから、島根県では、2009年からRubyを中核にしたIT産業振興、地域活性化に取り組んでいるという。
このRubyを、組み込みシステム向けに軽量化したものが「mruby/c」だ。ITOCと九州工業大学の田中和明准教授が共同で開発したもので、プログラム実行に必要なメモリ消費量が約40kBと、1チップマイコンでも動作するため、IoTデバイスの手軽な導入に貢献する。
例えば工業用ミシンの設計、製造を行うJUKI松江では、工業用ミシンの補助装置にmruby/cを採用。従来装置と比べてサイズは50%小型化、コストは25%削減、不良率は80%低減といった効果をあげたという。
ViXionの自動でピントを調節するアイウェア「ViXion01S」も、mruby/cを採用した初のコンシューマー製品として展示されていた。ほかにもmruby/cを標準搭載したマイコンボードを用意し、島根県内の学校でのIT教育に活用するなど、さまざまな事例を紹介する。
IT企業や人材の誘致も進んでいて、2025年4月時点での島根県内のIT事業従事者は1985人にのぼるという。ITOCの担当者は「EdgeTech+を通じて、島根県のITに注力する取り組みを知ってもらいたい」と語っていた。
関連記事
 組み合わせ最適化がエッジで解ける「量子インスパイア系」ソリューション
組み合わせ最適化がエッジで解ける「量子インスパイア系」ソリューション
東芝情報システムは「EdgeTech+ 2025」(2025年11月19〜21日、パシフィコ横浜)に出展し、量子コンピュータ研究をもとにした組み合わせ最適化ソリューションを紹介した。小さい計算リソースにも対応し、組み込み機器上で実行できるものだ。 貴重な半導体チップが集結! 「チップミュージアム」写真で紹介
貴重な半導体チップが集結! 「チップミュージアム」写真で紹介
組込み技術/エッジテクノロジーの展示会「EdgeTech+ 2025」(2025年11月19〜21日/パシフィコ横浜)では、特別企画として歴史的な半導体チップを展示する「チップミュージアム mini#」が登場した。その一部を写真で紹介しよう。 電動歯ブラシもAI対応に NordicのワイヤレスSoCが実現
電動歯ブラシもAI対応に NordicのワイヤレスSoCが実現
Nordic Semiconductorは「EdgeTech+ 2025」に出展し、超低電力ワイヤレスSoC(System on Chip)「nRF54シリーズ」を使ったAI対応電動歯ブラシや、パワーマネジメントIC(PMIC)「nPMシリーズ」採用の充電不要スマートリングなどを展示した。 VLMもエッジで実現! FP4対応、低消費電力のエッジAIカメラSoC
VLMもエッジで実現! FP4対応、低消費電力のエッジAIカメラSoC
デジタルメディアプロフェッショナルは「EdgeTech+ 2025」に出展し、エッジAIカメラ向けSoC(System on Chip)「Di1」を紹介した。FP4に対応した独自開発のNPUを搭載し、低消費電力で高度なAI推論処理を実行できる。 家のリモコンが電池いらずに 省電力機器向けOPV
家のリモコンが電池いらずに 省電力機器向けOPV
フランスの太陽電池メーカーであるDracula Technologiesは「EdgeTech+ 2025」に出展し、同社製の有機薄膜太陽電池(OPV)「LAYER」シリーズの展示を行った。低消費電力機器での使用を想定していて、500ルクス以下で性能を発揮するという。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加
- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損
- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす
- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却