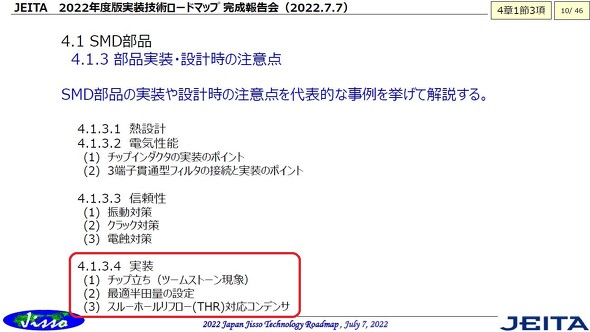適切なはんだ量の設定方法とスルーホールリフロー:福田昭のデバイス通信(458) 2022年度版実装技術ロードマップ(82)(1/2 ページ)
今回は、「4.1.3.4 実装」の後半2つの項目である「適切なはんだ量の設定」と「スルーホールリフロー(THR)対応コンデンサ」について解説する。
適切な量のはんだペーストを印刷することが不良を減らす
電子情報技術産業協会(JEITA)が3年ぶりに実装技術ロードマップを更新し、「2022年度版 実装技術ロードマップ」(書籍)を2022年7月に発行した。本コラムではロードマップの策定を担当したJEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会の協力を得て、ロードマップの概要を本コラムの第377回からシリーズで紹介している。
第448回からは、第4章「電子部品」の概要説明を始めた。前回は、4番目の項目である「4.1.3.4 実装」の概要前半をご報告した。「4.1.3.4 実装」はリフローはんだ付けに関する、「(1)チップ立ち」と「(2)適切なはんだ量の設定」「(3)スルーホールリフロー(THR)対応コンデンサ」の3つの項目で構成される。前回は「(1)チップ立ち」の概略を説明した。今回は「(2)適切なはんだ量の設定」と、「(3)スルーホールリフロー(THR)対応コンデンサ」の概要をご報告する。
コネクタにおけるはんだ付け不良と適切なはんだ量の設定例
前回でも述べたように、「チップ立ち」を含めたリフローはんだ付け不良を防ぐには、はんだペーストの印刷量を最適化する必要がある。
例えばコネクタの場合、印刷したはんだペーストの量が過剰だと、リード間にはんだブリッジが発生したり、コネクタのコンタクト部分にはんだが上昇してくる「はんだ上がり」が起こったりする。逆にはんだ量が少ないと、コネクタの接続強度が不足する恐れがある。
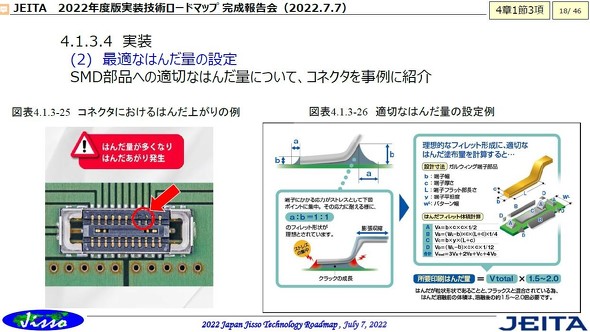 最適なはんだ量の設定事例。左はコネクタにおける「はんだ上がり」の発生例。右は適切なはんだ量の設定例[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)
最適なはんだ量の設定事例。左はコネクタにおける「はんだ上がり」の発生例。右は適切なはんだ量の設定例[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)はんだペーストの適切な印刷量は諸条件によって変わる。またノウハウに属する部分も存在する。一言でまとめることは難しい。適切なはんだ量の算出方法には例えば、はんだフィレットの理想的な形状から、寸法測定によってはんだの体積を求める方法がある。ただしはんだペーストにはフラックスが含まれているので、実際にはフィレットの体積よりも多くのはんだペースト(フィレット体積の1.5倍〜2.0倍とされる)を印刷しておく必要がある。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす
- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加
- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか