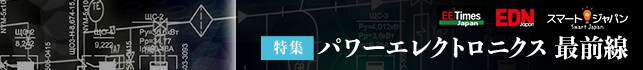SiCの20年 ウエハーは「中国が世界一」に、日本の強みは何か:京都大学 工学研究科 教授 木本恒暢氏(2/3 ページ)
今後の課題は欠陥による抵抗と信頼性
――20年前から現在まで残っている課題はありますか。
木本氏 ずっと残っている課題は、SiC MOSFETにおけるSiCと酸化膜(SiO2)との接合界面に多数存在する欠陥だ。これについては世界中で研究が続けられているが、20年で大きな進展があったかは疑問だ。Si比で100倍以上もの欠陥があり、SiCはこのせいで本来の実力を発揮できていない。理想的な特性よりも2〜3倍抵抗が高い状態だ。
現時点でもSiより性能が良いので利用が拡大しているが、この抵抗を半分にできれば、チップ面積も半分にできる。そうすれば歩留まりも向上するので、コストは半分以下になり、Siとほぼ同等になる。そうなればSiCは爆発的に普及し、省電力化が飛躍的に進んでいくだろう。
そのためにはブレークスルーが必要で、アカデミアの果たすべき役割は大きい。基礎に立ち返った研究がますます大切になるだろう。最近は第一原理計算など、高精度でさまざまな欠陥の構造や性質を予測する学問も立ち上がっているので、それらも活用しながら「もう一度研究してみる」ことが重要だ。
加えて、SiCパワーデバイスの実用化が進むことで新たに顕在化してきたのは、信頼性の課題だ。パワーデバイスは通常動作時だけでなく、事故発生時の信頼性も重視される。SiCはSiに比べてオン抵抗が低いので、負荷短絡が発生した際に大電流が流れてトランジスタが破壊されてしまう危険性があり、保護回路の工夫が必要だ。こうした信頼性が今後の課題だろう。
SiCウエハーは「中国がトップ」 日本は最先端デバイス開発で先行
――現在のSiC産業における中国勢の躍進や日本企業の状況をどう見ていますか。
木本氏 現在はSiCウエハーの大口径化と高品質化、低コスト化、全てで中国が世界トップだと見ている。中国がSiCの研究開発に注力し始めたのは2010年代からで、世界でも後発の部類だが、シミュレーションや実験を集中的に行ったのだろう。1980年代から研究を行ってきた日本や米国、ドイツは追い抜かれてしまった。ただし、中国は全く新しい手法を生み出したわけではなく、あくまで投入したリソースの違いだ。日本も同レベルには到達できるはずなので、頑張ってもらいたい。
中国はデバイス開発でも急ピッチで成長しているが、最先端のデバイス開発では日本企業がトップクラスで、まだ負けていない。1〜2世代、中国に先行している状況だ。かと言って「デバイス開発は優秀だがウエハーは中国から買うしかない」という状況は戦略的にも望ましくないので、日本企業にはウエハーの研究開発も進めてもらいたい。
日本はウエハーメーカーからデバイスメーカーまで、パワーデバイスのエコシステムが完成している。ウエハーでは信越化学工業やSUMCO、デバイスでは東芝デバイス&ストレージや三菱電機、ローム、ルネサス エレクトロニクスといった企業がSiから積み上げてきた経験値がある。パワーデバイスはチップではなくモジュールやシステムとして売ることが多いので、ソリューションとして構成できる人材がいて技術があることが日本の強みだ。
一方、中国は国内企業の経験値がまだ十分ではない。現在は米国企業でパワーデバイス開発に携わった技術者などが帰国して開発を進めているのだろう。差は縮まってきているが、モジュールやシステムとして構成する力がどれほどあるかはまだ見えない。
――今後、SiCパワーデバイスに関わる企業がグローバルに競争力を保つためには何が必要だと思いますか。
木本氏 乱暴な言い方をすると、今後はベストタイミングで大きな投資をしたところが勝つことになるだろう。難しい判断だが、日本企業はタイミングを逸することなく、かつ中途半端ではなく海外企業に勝てるだけの規模で投資をしなければ、世界のスピードについていけなくなる。
加えて、低コスト化も大きな課題だ。現在は信頼性確保のためにかなりの時間とコストをかけて出荷前のスクリーニングを行っている。そこを省けるようにするなど低コスト化のための技術開発はまだ残っていて、ここは欠陥についてのノウハウを蓄積してきた日本が強みを発揮できる領域だと思う。
現在はEV市場の一時的な減速で影響を受けている企業もあるが、次の波が来たときにすぐ製品を出荷できるよう、製造ラインの整備や技術向上は進める必要があるだろう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加
- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損
- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす
- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却