25Gbpsの高速光伝送を、5mW/1Gbpsの低消費電力で実現:新技術 CPU間光伝送(2/2 ページ)
» 2015年02月23日 15時30分 公開
[EE Times Japan]
1.8Vで動作可能に
今回開発した技術では、CPUからの送信信号が−1、+1に変化するタイミングに限定して信号を増幅することで、1.8V程度の振幅を断続的に発生させている。これにより、3.3Vよりも低い1.8Vの電源電圧で動作させることが可能になった。さらに、データが変化しないところは小振幅で電力を使わないので、さらなる低消費電力化が図れる。
仕組みは次の通りだ。
- 送信データと、それを遅延させたデータを、−α(0<α<1)倍したものを足し合わせる
- これにより、送信データが−1から+1に変化する場合、+1が+1+αに増幅される
- 送信データが+1から−1に変化する場合、−1が−1−αに変化する
同技術により、25Gbpsの高速伝送を1Gbps当たり5mWで実現できることを確認したという。この消費電力は従来の約半分である。
富士通は、この技術をCPUや光モジュールのインタフェース部などに適用し、2018年度の実用化を目指す。また、複数の光送受信回路を並べた、毎秒テラビット級の高速伝送を実現する、サーバやスパコンの高性能化が期待できるとしている。
関連記事
 CPU間データ通信速度で32Gbpsを達成、富士通研が新たな送受信回路を開発
CPU間データ通信速度で32Gbpsを達成、富士通研が新たな送受信回路を開発
富士通研究所は、CPU間のデータ通信速度を従来比で約2倍となる32ギガビット/秒(Gbps)に高速化できる送受信回路を開発した。次世代サーバ向けCPUに適用し、2014年ごろの実用化を目指す。 400Gビット級光伝送技術の実用化にめど、NTTなど3社が開発
400Gビット級光伝送技術の実用化にめど、NTTなど3社が開発
NTTとNEC、富士通の3社は、チャネル当たり毎秒400Gビット級の光伝送技術の実用化にめどをつけた。開発した技術を光送受信装置に実装すれば、既存の光ファイバを活用して、従来に比べて4倍の光伝送を実現することが可能となる。 Intelが100Gbpsの光モジュールを開発、Open Compute Summitでお披露目
Intelが100Gbpsの光モジュールを開発、Open Compute Summitでお披露目
Intelが100Gbpsのデータ転送速度を実現可能なシリコンフォトニクスベースのモジュールを発表した。そのお披露目の場となった「Open Compute Summit」では各社から、大規模なデータセンター向けのさまざまな革新的技術が発表された。 「光FPGA」の実動デモをAlteraが披露、100GbEのトラフィックを伝送
「光FPGA」の実動デモをAlteraが披露、100GbEのトラフィックを伝送
FPGA大手ベンダーのAlteraは、光インタフェースを搭載したFPGAを開発し、その動作デモを実演した。通信機器内でFPGAが入出力する高速データの伝送を、銅線を使った電気通信から光ファイバーを利用する光通信に置き換えることを狙う。ネットワークインフラの帯域幅の急拡大に対応する取り組みだ。 産総研、生きた細胞の機能を光エネルギーで操作できる技術を開発
産総研、生きた細胞の機能を光エネルギーで操作できる技術を開発
生体透過性の高い近赤外レーザーで熱と活性酸素種を発生する有機色素と、カーボンナノホーンから成る分子複合体(ナノモジュレーター)を作製。この分子複合体を用いて、生きた細胞の機能を操作できる光制御技術を開発した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special ContentsPR
特別協賛PR
スポンサーからのお知らせPR
Special ContentsPR
Pickup ContentsPR
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす
- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加
- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか
Special SitePR
あなたにおすすめの記事PR

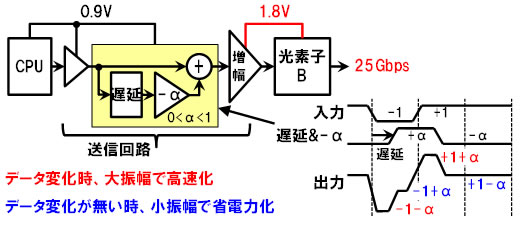 図3 振幅を大きくする仕組み 出典:富士通
図3 振幅を大きくする仕組み 出典:富士通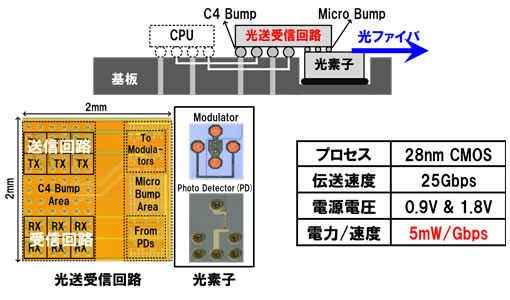 図4 開発した光送受信回路のチップ写真と、チップの特性 出典:富士通
図4 開発した光送受信回路のチップ写真と、チップの特性 出典:富士通