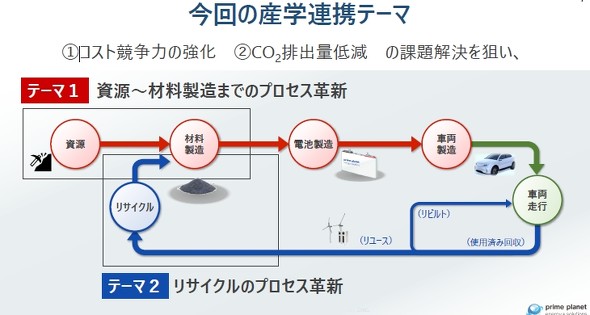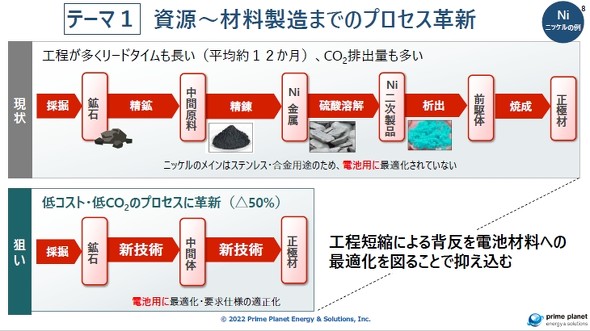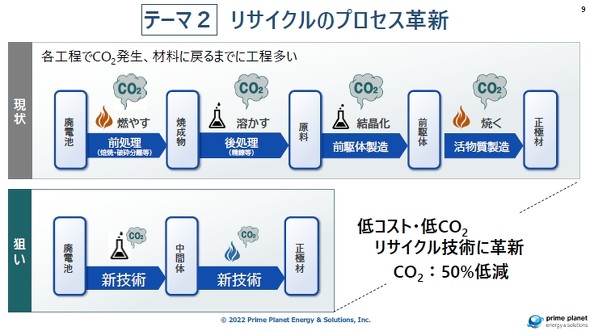電池の材料開発や製造プロセス開発で産学連携:CO2排出量と生産コストを大幅低減(2/2 ページ)
2つのテーマを掲げて共同研究
こうした状況を踏まえ、今回の産学連携では2つのテーマを掲げ、共同研究に取り組むことにした。そのテーマとは「資源開発から電池材料の開発、製造までのプロセス革新」と、「電池廃材や廃電池リサイクルのプロセス革新」である。協定の契約期間は2023年12月末までとなるが、状況によっては契約延長の可能性もあるという。
具体的な取り組みはこうだ。「資源開発から電池材料の開発、製造までのプロセス革新」では、より電池用途に特化したプロセスを新たに構築する。これによって、CO2排出量の低減や生産コストの低減、材料生成のリードタイム短縮を実現していく。
このため、ニッケルやリチウム、コバルトの金属資源開発、精錬工程から電池材料の開発製造に至るまで、一気通貫で既存のプロセスを見直す。例えば、正極に用いられるニッケルの製造工程はリードタイムが平均約12カ月と長い。CO2排出量も多いという。
この理由は、ニッケルの主な用途がステンレス・合金向けのため、製造プロセスが電池用に最適化されていないためだという。そこで、電池用に特化したプロセスを新たに構築することで、「CO2排出量の低減」「生産コスト低減」「材料生成リードタイムの短縮」を実現していく。
「電池廃材や廃電池リサイクルのプロセス革新」では、電池製造時の廃材や使用後の廃電池を、効率よくリサイクルするための技術を開発していく。このため、総合的なレアメタル精錬技術を保有する大学と電池メーカー、さらにはリサイクル回収や処理を担う商社が協力し、リサイクル過程で発生するCO2排出量やリサイクルコストの大幅低減に取り組む。
共同研究に関する投資額は非公表とし、具体的な金額は明らかにしなかったが、「それなりの規模で投資する。研究費用を積み増す可能性もある」(岡部氏)という。これらの研究成果は2025年までに実用化したい考えで、2030年には電池産業全体でCO2排出量を、現状に対し80%削減するのが目標である。
関連記事
 カゴメ格子強磁性体Fe3Snで巨大な磁気熱電効果
カゴメ格子強磁性体Fe3Snで巨大な磁気熱電効果
東京大学の研究グループは、東北大学らの研究グループと協力し、鉄(Fe)原子がカゴメ格子を形成した強磁性体Fe▽▽3▽▽Snの多結晶体において、巨大な磁気熱電効果(異常ネルンスト効果)が発現することを発見した。その効果の起源は、「ノーダルプレーン」と呼ばれる電子状態であることも明らかにした。 小型積層マグネットで17.89Tの強磁場捕捉に成功
小型積層マグネットで17.89Tの強磁場捕捉に成功
東京大学と東北大学、フジクラの共同研究グループは、高性能コーテッドコンダクターを用いて小型の積層マグネットを作製し、17.89Tという強磁場を捕捉することに成功した。磁場捕捉に要する時間もわずか75分で、従来に比べ15分の1以下と大幅短縮した。 低下した全固体電池の性能を加熱処理で大幅改善
低下した全固体電池の性能を加熱処理で大幅改善
東京工業大学は、東京大学や産業技術総合研究所、山形大学らと共同で、低下した全固体電池の性能を、加熱処理だけで大幅に改善させる技術を開発した。電気自動車用電池などへの応用が期待される。 東京大ら、高温で高配向有機半導体ナノ薄膜を製造
東京大ら、高温で高配向有機半導体ナノ薄膜を製造
東京大学と物質・材料研究機構および、協和界面科学の共同研究グループは、200℃近い高温ウェットプロセスで、配向性の高い有機半導体ナノ薄膜を製造することに成功した。 東芝、入出力性能を高めた大容量タイプセルを開発
東芝、入出力性能を高めた大容量タイプセルを開発
東芝は、リチウムイオン二次電池「SCiB」の新製品として、「高入出力性能」と「高エネルギー密度」を両立した「20Ah-HPセル」を開発、受注を始めた。 NIMSら、500Wh/kg級のリチウム空気電池を開発
NIMSら、500Wh/kg級のリチウム空気電池を開発
物質・材料研究機構(NIMS)は、重量エネルギー密度が500Wh/kg級のリチウム空気電池をソフトバンクと共同開発し、室温での充放電反応を実現した。開発したリチウム空気電池は、「エネルギー密度」と「サイクル数」が世界最高レベルだという。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
- DDR5の異常な価格急騰はなぜ起きた? 推測できるシナリオは
- Rapidus、600mm角インターポーザーパネルを初披露 NVIDIAの受託にも意欲
- 中国がEUV試作機 世界の半導体市場は完全に分断されるのか
- 半導体の性能向上は「AI演算の需要」を満たせるのか
- クリーンスーツ 隠れた特技 早着替え……あるある満載の半導体かるたが完成
- Rapidus、千歳で製造した2nm GAAトランジスタの試作品を初展示
- 2026年のHBM市況、カギを握るのは最新世代「HBM4」
- GaN特性は音にも効く? GaN FETのオーディオアンプが出始めた
- ニデックの経営「岸田社長に全て委ねる」、代表取締役辞任の永守氏
- EUV露光に残された課題――ペリクルの現在地と展望とは