EE Times Japan >
LSI >
AMDが開発した「Zen4」CPUダイのメモリ構成:福田昭のデバイス通信(374)(2/2 ページ)
» 2022年12月02日 11時30分 公開
[福田昭,EE Times Japan]
EPYCプロセッサの3次キャッシュ容量は前世代の1.5倍に拡大
3次キャッシュ(L3キャッシュ)あるいはラストレベルキャッシュ(LLC)は、CCDの各CPUコアが共有するシェアードキャッシュである。CPUコア当たりの記憶容量は4Mバイトで、Zen3と変わらない。CCDはZen3とZen4ともに8個のCPUコアを搭載する。このため、CCDが内蔵する3次キャッシュの記憶容量は32Mバイトのままである。
 Zen4プロセッサの3次キャッシュ(ラストレベルキャッシュ)は各CPUコアが共有する。記憶容量はCPUコア当たりで4Mバイトであり、全体では32Mバイトとなる。なお「CCX(Core Complex)」はCPUコアと2次キャッシュ、3次キャッシュをまとめたマクロ(IP)を意味する。外部とやりとりする入出力回路をCCXに加えたシリコンダイ(ミニダイあるいはチップレット)が「CCD(Core Complex Die)」である[クリックで拡大] 出所:AMD
Zen4プロセッサの3次キャッシュ(ラストレベルキャッシュ)は各CPUコアが共有する。記憶容量はCPUコア当たりで4Mバイトであり、全体では32Mバイトとなる。なお「CCX(Core Complex)」はCPUコアと2次キャッシュ、3次キャッシュをまとめたマクロ(IP)を意味する。外部とやりとりする入出力回路をCCXに加えたシリコンダイ(ミニダイあるいはチップレット)が「CCD(Core Complex Die)」である[クリックで拡大] 出所:AMDただし第4世代EPYCは1個のプロセッサが最大で12枚のCCDを搭載する。第3世代EPYCが最大で8枚であったから、プロセッサが搭載可能な3次キャッシュの記憶容量は第3世代EPYCの256Mバイトから、第4世代EPYCでは384Mバイトと1.5倍に拡大した。
なお前世代(第3世代)のEPYCプロセッサは、CCD当たりの3次キャッシュをシリコンダイ積層技術によって96Mバイトに拡大できた。CCDと、64Mバイトの3次キャッシュダイをハイブリッド接合技術によって積層する。AMDはこの技術を「3D V-Cache」と呼んでいる。この技術を採用した第3世代EPYCプロセッサは最大で768Mバイトと巨大な3次キャッシュを備える。
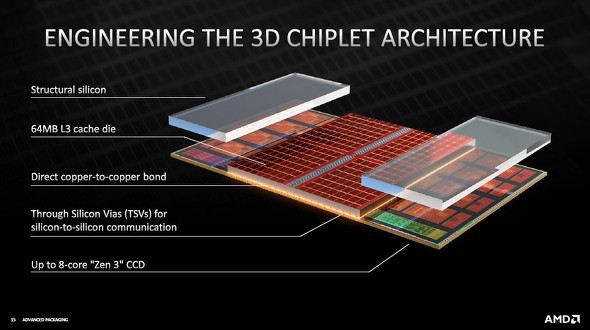 64Mバイトの3次キャッシュダイをハイブリッド接合技術によってCCDと積層する「3D V-Cache」の構造図[クリックで拡大] 出所:AMDが2021年8月22日に国際学会「Hot Chips 33」のチュートリアルセッションで発表したスライド
64Mバイトの3次キャッシュダイをハイブリッド接合技術によってCCDと積層する「3D V-Cache」の構造図[クリックで拡大] 出所:AMDが2021年8月22日に国際学会「Hot Chips 33」のチュートリアルセッションで発表したスライド⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧
関連記事
 AMDが開発した第4世代のZenコア「Zen4」の概要
AMDが開発した第4世代のZenコア「Zen4」の概要
今回は、Zenアーキテクチャのx86互換64ビットCPUコアで第4世代となる「Zen4」の概要をご紹介する。 AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表
AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表
AMDは2022年11月10日(米国時間)に米国カリフォルニア州サンフランシスコで新製品発表会「together we advance_data centers」を開催し、サーバ向けプロセッサの新製品「EPYC 9004シリーズ」の販売を開始した。 HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少
HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少
米Western Digitalの「2023会計年度第1四半期」(2022年7月〜9月)を紹介する。 HDD大手Seagateの四半期業績は2桁%の減収減益に
HDD大手Seagateの四半期業績は2桁%の減収減益に
米Seagate Technologyの2023会計年度第1四半期(2022年7月〜9月)の業績を紹介する。 携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)
携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)
今回はフラッシュメモリを記憶媒体とする携帯型デジタルオーディオプレーヤー(DAP:Digital Audio Player)を扱う。時期は1997年〜1998年である。 ビデオカメラの記録媒体にフラッシュメモリが進出(2003年〜2004年)
ビデオカメラの記録媒体にフラッシュメモリが進出(2003年〜2004年)
今回は、動画記録用の媒体にフラッシュメモリを利用したデジタルビデオカメラを報告する。年表の時期は2003年〜2004年である。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special ContentsPR
特別協賛PR
スポンサーからのお知らせPR
Special ContentsPR
Pickup ContentsPR
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす
- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加
- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか
Special SitePR
あなたにおすすめの記事PR

