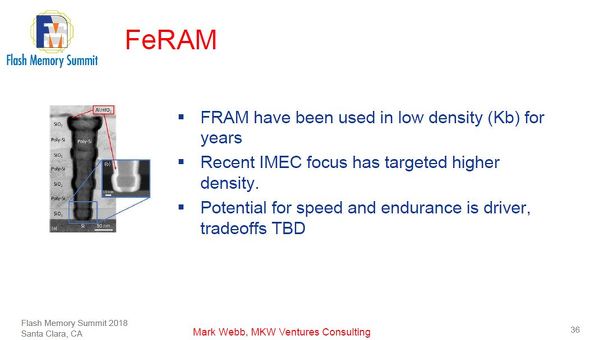新材料で次々世代を狙う「強誘電体メモリ(FeRAM)」:福田昭のストレージ通信(156) 半導体メモリの技術動向を総ざらい(15)(2/2 ページ)
60年を超える歴史を有する強誘電体メモリの研究開発
強誘電体を使った不揮発性メモリの研究開発は、60年を超える長い歴史を有する(詳しくは参考記事「強誘電体メモリ研究の歴史(前編)〜1950年代の強誘電体メモリ」と「強誘電体メモリ研究の歴史(後編)〜1990年代以降の強誘電体メモリ」を参照)。研究開発の始まりは1950年代前半である。圧電性セラミックスの強誘電体である、チタン酸バリウム(BaTiO3)を使ったキャパシターを記憶素子に応用し、キャパシターをクロスポイント構造に配列したメモリが研究された。これを「第1世代」の強誘電体メモリと呼ぶ。
第1世代の強誘電体メモリは動作が安定しないという問題を解決できず、研究開発は冬の時代を迎える。研究開発が再び活発になるのは、1980年代後半からである。圧電セラミックスの強誘電体であるPZT(チタン酸ジルコン酸鉛:PbZrTiO3)を使ったキャパシターを記憶素子とした。記憶素子とセル選択トラジスタを組み合わせたメモリセルにより、1990年代には不揮発性メモリの製品化が始まる。
PZTは、動作電圧がやや高いという弱点を抱えていた。動作電圧が低くても適用できる強誘電体材料として、これも圧電セラミックスのSBT(タンタル酸ビスマス酸ストロンチウム:SrBi2Ta2O9)がPZTと同様に記憶素子として研究された。PZTと同様に、セル選択トランジスタと組み合わせたメモリセルにより、1990年代に不揮発性メモリとして製品化された。これらPZTとSBTによる強誘電体メモリを「第2世代」と呼ぶ。
PZTとSBTを使った強誘電体メモリの研究開発は、2000年代に入ると下火になっていく。その大きな理由は、「サイズ効果」と呼ばれる微細化の限界に突き当たったことだ。PZTとSBTはいずれも、厚みが200nm以下になると強誘電体としての性質が弱まるという問題を抱えていた。これは半導体の製造技術だと、130nm世代が微細化の限界であることを意味する。このサイズ効果によって第2世代の微細化は130nm世代にとどまるとともに、製品化された不揮発性メモリの記憶容量は、最大でも4Mビット〜8Mビットとかなり小さな値が限界となってしまった。
現在の研究開発は「第3世代」の強誘電体が主流
この限界を突破したのが、「10nm前後に薄くしても強誘電体としての性質を維持する」材料の発見である(詳しくは参考記事「強誘電体メモリが再び注目を集めている、その理由」を参照)。材料はハフニウム酸化物(HfOx)であり、発見が公表されたのは2011年のことだ。
ハフニウム酸化物は、高い誘電率を有する絶縁材料として半導体製造の世界では既に良く知られており、2011年当時は先端ロジック製品のMOSFETでゲート絶縁膜に使われていた。厳密には、高誘電体であるハフニウム酸化物に、ある特定の条件を加えると、強誘電体になることが分かった、という発見である。
このハフニウム酸化物を使った強誘電体メモリを「第3世代」と呼ぶ。現在の強誘電体メモリの研究開発は主に、ハフニウム酸化物が使われている。
2011年に強誘電体としてのハフニウム酸化物が発見されてからの動きはかなり目まぐるしい。2012年には、1T1C方式のメモリセルが試作された。2014年には1T方式のメモリセル、すなわちFeFETが発表されている。FeFETを使った小容量の不揮発性メモリも試作済みである。いずれも学会発表であり、製品化の発表はまだないようだ。
(次回に続く)
⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧
関連記事
 ハードディスク業界の国内最大イベント、2019年は7月末に開催(前編)
ハードディスク業界の国内最大イベント、2019年は7月末に開催(前編)
2019年7月25〜26日に東京都内で開催される「国際ディスクフォーラム」の開催プログラムが決定した。前後編に分けて、プログラムの内容を紹介していく。 次々世代の不揮発性メモリ技術「カーボンナノチューブメモリ(NRAM)」
次々世代の不揮発性メモリ技術「カーボンナノチューブメモリ(NRAM)」
次世代メモリの有力候補入りを目指す、カーボンナノチューブメモリ(NRAM:Nanotube RAM)について解説する。NRAMの記憶原理と、NRAMの基本技術を所有するNanteroの開発動向を紹介しよう。 抵抗変化メモリ(ReRAM)の製品化動向と製造コスト見通し
抵抗変化メモリ(ReRAM)の製品化動向と製造コスト見通し
抵抗変化メモリ(ReRAM)の製品化動向と製造コスト見通しを紹介する。特に、ReRAMの製品化で大きな役割を果たしているベンチャー企業各社を取り上げたい。 「シリコン・サイクル」の正体
「シリコン・サイクル」の正体
今回は、「シリコン・サイクル」について解説する。シリコン・サイクルの4つの状態と、シリコン・サイクルが備える特性を紹介する。 最先端プロセスでも歴然の差! チップ面積は半導体メーカーの実力を映す鏡
最先端プロセスでも歴然の差! チップ面積は半導体メーカーの実力を映す鏡
今回は、“チップ面積”に注目しながら2018〜2019年に発売された最新スマートフォン搭載チップを観察していく。同じ世代の製造プロセスを使用していても、チップ面積には歴然たる“差”が存在した――。 中国 紫光集団がDRAM事業設立へ
中国 紫光集団がDRAM事業設立へ
中国の国有企業であるTsinghua Unigroup(清華紫光集団)が、新しいDRAM企業を設立した。中国は、米国との貿易摩擦が続く中、半導体技術の国外依存度を少しでも下げようとしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
- ローム、デンソーによる買収提案は「事実」
- ロームとデンソー、東芝、三菱電機……国内パワー半導体再編の行方
- 25年Q4の半導体企業ランキング、キオクシアが13位に上昇
- 村田製作所に不正アクセス 社内外情報が流出の可能性
- 法的責任も調査、ニデック不正会計の衝撃 減損2500億円の恐れ
- ニデック、至るところに会計不正「最も責めを負うべきは永守氏」
- IntelとSambaNova、提携の行く末――「最もあり得るシナリオ」は?
- ミニダイ(チップレット)間接続におけるSTCO
- 25年4QのDRAM市場、SamsungがSKから首位奪還
- 目指すは500nm RDL 太陽HDがimecと挑む次世代パッケージング材料