「CoWoS」の標準アーキテクチャが顧客による開発期間を短縮:福田昭のデバイス通信(336) TSMCが開発してきた最先端パッケージング技術(9)(2/2 ページ)
広帯域メモリ「HBM」とSoCを混載する「CoWoS_S」の構成とレイアウトを標準化
「CoWoS_S」の主流は、広帯域メモリモジュール「HBM(High Bandwidth Memory)」と大規模なSoCを混載した高性能サブシステムである。Siインターポーザを介してHBMとSoCを接続することで、広帯域のメモリアクセスを実現する。
「HBM」の仕様は世代ごとに共通規格が定められている。製品への普及は第2世代の「HBM2」から始まった。次の世代はHBM2の強化版「HBM2E」である。さらに次の世代は「HBM3」で、大容量化と広帯域化が進む。加えて「CoWoS_S」に搭載するHBMの数量は増加し、Siインターポーザの面積は拡大し、SoCの製造技術は微細化する。SoCはシングルダイからチップレット、さらにはSoIC(System on Integrated Chips)へと形態を変える。「CoWoS_S」を構成する要素技術は増加し、かつ複雑になる。
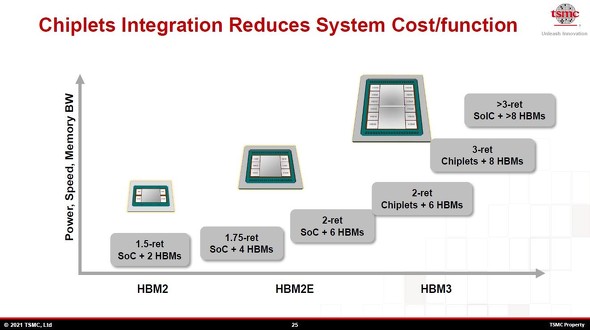 広帯域メモリモジュール「HBM」の進化(横軸)と、対応する「CoWoS_S」の消費電力、速度、メモリ帯域の推移(縦軸)[クリックで拡大] 出所:TSMC(Hot Chips 33の講演「TSMC packaging technologies for chiplets and 3D」のスライドから)
広帯域メモリモジュール「HBM」の進化(横軸)と、対応する「CoWoS_S」の消費電力、速度、メモリ帯域の推移(縦軸)[クリックで拡大] 出所:TSMC(Hot Chips 33の講演「TSMC packaging technologies for chiplets and 3D」のスライドから)そこでTSMCは、顧客である半導体ベンダーが「CoWoS_S」を採用したサブシステムを素早く開発できるように、構成とレイアウトを標準化した「CoWoS_S STAR(STandard ARchitecture)」を提供している。HBM2に対応する「STAR 1.0」と、HBM2Eに対応する「STAR 2.0」を用意した。
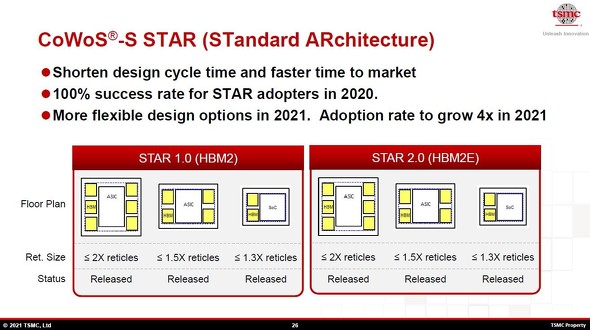 SoCとHBMを混載する「CoWoS_S」の構成を標準化した「CoWoS_S STAR」の概要[クリックで拡大] 出所:TSMC(Hot Chips 33の講演「TSMC packaging technologies for chiplets and 3D」のスライドから)
SoCとHBMを混載する「CoWoS_S」の構成を標準化した「CoWoS_S STAR」の概要[クリックで拡大] 出所:TSMC(Hot Chips 33の講演「TSMC packaging technologies for chiplets and 3D」のスライドから)標準化しているのはSiインターポーザの最大寸法とHBMの個数、それからシリコンダイのレイアウトなどである。最大構成と中間の構成、最小構成の3つの基本仕様を顧客は選べる。
最大構成は、レチクルの2倍に相当する露光面積のSiインターポーザを最大寸法とする。SoC(あるいはASIC)を中央にレイアウトし、その左右に3個ずつのHBMを配置する。中間の構成はレチクルの1.5倍に相当する露光面積をSiインターポーザの最大寸法とする。SoCは中央にレイアウトし、その左右に2個ずつのHBMを配置する。最小構成はレチクルの1.3倍に相当する露光面積をSiインターポーザの最大寸法とする。SoC(あるいはASIC)の側面に沿って2個のHBMを配置している。
最大構成から最小構成までの標準仕様は、HBM2対応の「STAR 1.0」とHBM2E対応の「STAR 2.0」で変わらない。「STAR 1.0」の開発資産を「STAR 2.0」で再利用することを意識しているように見える。
(次回に続く)
⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧
関連記事
 TSMCが語る「N3」ノードの詳細
TSMCが語る「N3」ノードの詳細
TSMCは現在、「N5」プロセスノード適用製品の生産を順調に拡大しているところだが、それをさらに進化させた「N4」ノードの量産を2021年中に開始する予定だと発表した。また、N4よりもさらなる技術的飛躍を実現するとみられる「N3」ノードについても、2022年後半には量産を開始する計画だという。 ウエハースケールの超巨大プロセッサを実現した「InFO」技術
ウエハースケールの超巨大プロセッサを実現した「InFO」技術
「InFO」技術を改良した2種類のパッケージのうち、ウエハー規模の巨大なパッケージング技術「InFO_SoW」を解説する。 多層配線のビア抵抗を大幅に低減する「スーパービア」
多層配線のビア抵抗を大幅に低減する「スーパービア」
今回は、奇数番号(あるいは偶数番号)で隣接する配線層(2層上あるいは2層下の配線層)を接続するビア電極の抵抗を大幅に下げる技術、「スーパービア(supervia)」について解説する。 モバイル向け小型薄型パッケージ「InFO」が進化
モバイル向け小型薄型パッケージ「InFO」が進化
TSMCが開発してきた先進パッケージング技術の最新動向を紹介する。始めは全体のトレンドを示す。 「システム・製造協調最適化(STCO)」の実現技術(前編)
「システム・製造協調最適化(STCO)」の実現技術(前編)
7nm以降の技術ノードでは、「設計・製造協調最適化(DTCO)」だけでなく、「システム・製造協調最適化(STCO:System Technology Co-Optimization)」も利用することでPPAあるいはPPACのバランスを調整することが求められるようになってきた。 「システム・製造協調最適化(STCO)」の実現技術(後編)
「システム・製造協調最適化(STCO)」の実現技術(後編)
本シリーズの最終回となる今回は、前回に続き「システム・製造協調最適化(STCO)」を解説する。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
- TSMCが2nmプロセス量産を開始、台湾2工場で
- 酸化ガリウムデバイス向け4インチウエハー量産へ
- ソニー・ホンダモビリティが次世代「AFEELA」を初公開、28年以降に米国投入へ
- 50年前の「初代ダイシングソー」実物と最新製品を展示、ディスコ
- 世界半導体市場、2029年に1兆米ドル規模へ 製造装置も成長継続
- 活版印刷で培った金属加工 1.4nmプロセス向けNILテンプレート、DNP
- SiCウエハー世界市場は2035年に5724億円規模へ 中国メーカーが攻勢
- DRAM契約価格さらに55〜60%上昇へ 2026年1〜3月
- 富士電機とボッシュ、互換性あるSiC車載モジュール開発へ
- 中国がEUV試作機 世界の半導体市場は完全に分断されるのか
