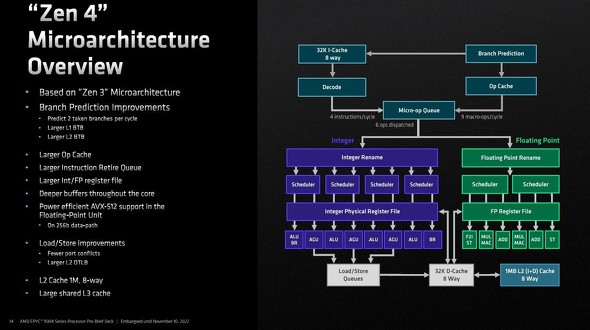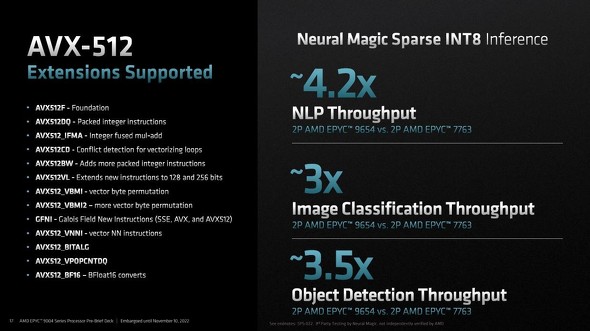AMDが開発した第4世代のZenコア「Zen4」の概要:福田昭のデバイス通信(373)(2/2 ページ)
「Zen3」に数多くの改良を加えた「Zen4」のマイクロアーキテクチャ
「Zen4」のマイクロアーキテクチャは、前世代の「Zen3」をベースに数多くの改良を加えた。分岐予測の強化(サイクル当たりに2つの分岐を予測、分岐先バッファ(BTB)の拡大)、マイクロOpキャッシュ(内部命令キャッシュ)の増量、命令リタイアキューの拡大、整数レジスタファイルと浮動小数点レジスタファイルの拡張、AVX-512命令セットのサポート、ロード/ストアの改良、2次キャッシュの拡大、などがある。
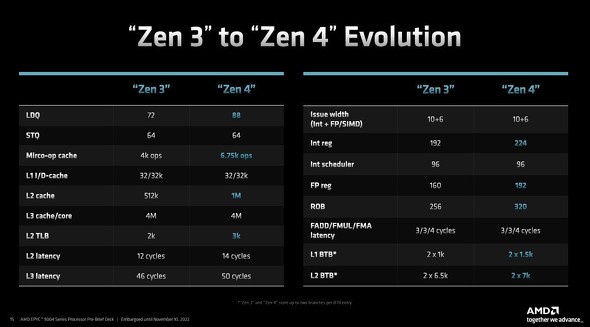 「Zen3」と「Zen4」の比較。Zen4では、ロードキュー(LDQ)のエントリ数を増やす、マイクロOpキャッシュが格納可能な命令数を増やす、2次(L2)キャッシュ容量を2倍に拡大、2次TLBのエントリ数を1.5倍に増加、整数レジスタファイルと浮動小数点レジスタファイルの増量、ROB(リオーダーバッファ)の増加、1次BTBと2次BTBの拡大などの改良がみられる[クリックで拡大] 出所:AMD
「Zen3」と「Zen4」の比較。Zen4では、ロードキュー(LDQ)のエントリ数を増やす、マイクロOpキャッシュが格納可能な命令数を増やす、2次(L2)キャッシュ容量を2倍に拡大、2次TLBのエントリ数を1.5倍に増加、整数レジスタファイルと浮動小数点レジスタファイルの増量、ROB(リオーダーバッファ)の増加、1次BTBと2次BTBの拡大などの改良がみられる[クリックで拡大] 出所:AMD特筆すべきは浮動小数点演算で256ビット幅のAVX-512拡張命令をサポートしたことだろう。AVX-512には数多くの命令セットがあり、Zen4ではVNNI(Vector Neural Network Instruction)命令やBFloat16命令といった機械学習の処理を高速化する命令をサポートする。
その結果、Zen3コアのプロセッサ(64コア構成のEPYC)に比べ、Zen4のプロセッサ(96コア構成のEPYC)は自然言語処理のスループットが約4.2倍、画像分類処理のスループットが約3倍、物体検出処理のスループットが約3.5倍と大きく向上したという。
5nmのFinFETプロセスでTSMCが製造
前回で述べたように、第4世代のEPYCプロセッサである「EPYC 9004」シリーズは8個のCPUコアを内蔵したミニダイ(チップレット)を入出力ミニダイとともに基板に搭載した。CPUコアを内蔵するミニダイ(CCD)は、Zen4コアとコアごとの2次キャッシュ、共有3次キャッシュ、入出力ダイとのインタフェース回路で構成される。製造技術は5nmのFinFETプロセス。製造担当企業はTSMCである。
AMDは新製品発表会「together we advance_data centers」で、Zen4コアと2次キャッシュを含めたシリコンの面積を3.84mm2としていた。8個のコアを搭載するので、単純計算では30.72mm2となる。これに32Mバイトの共有3次キャッシュとインタフェース回路を加えると、1枚のCCDが出来上がる。
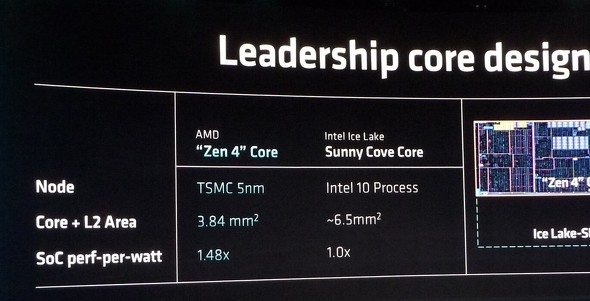 CPUコアと2次キャッシュを含めたシリコンの面積。Zen4と、Intelの10nmプロセスによるCPUコア(Sunny Cove)を比較した。2022年11月10日(米国時間)にAMDが開催した新製品発表会「together we advance_data centers」の講演を筆者が撮影したもの[クリックで拡大]
CPUコアと2次キャッシュを含めたシリコンの面積。Zen4と、Intelの10nmプロセスによるCPUコア(Sunny Cove)を比較した。2022年11月10日(米国時間)にAMDが開催した新製品発表会「together we advance_data centers」の講演を筆者が撮影したもの[クリックで拡大]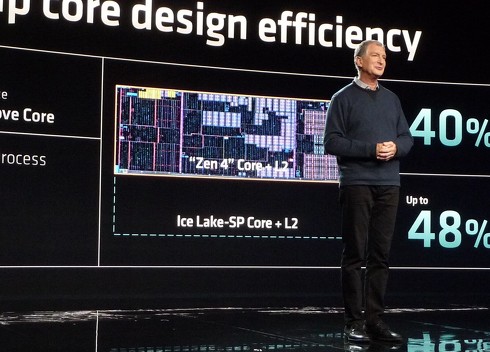 Zen4コアと2次キャッシュを含めたシリコンの回路レイアウト。2022年11月10日(米国時間)にAMDが開催した新製品発表会「together we advance_data centers」の講演を筆者が撮影したもの。中央はAMDのCTO兼EVP(テクノロジーおよびエンジニアリング担当)をつとめるMark Papermaster氏[クリックで拡大]
Zen4コアと2次キャッシュを含めたシリコンの回路レイアウト。2022年11月10日(米国時間)にAMDが開催した新製品発表会「together we advance_data centers」の講演を筆者が撮影したもの。中央はAMDのCTO兼EVP(テクノロジーおよびエンジニアリング担当)をつとめるMark Papermaster氏[クリックで拡大]⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧
関連記事
 AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表
AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表
AMDは2022年11月10日(米国時間)に米国カリフォルニア州サンフランシスコで新製品発表会「together we advance_data centers」を開催し、サーバ向けプロセッサの新製品「EPYC 9004シリーズ」の販売を開始した。 HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少
HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少
米Western Digitalの「2023会計年度第1四半期」(2022年7月〜9月)を紹介する。 携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)
携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)
今回はフラッシュメモリを記憶媒体とする携帯型デジタルオーディオプレーヤー(DAP:Digital Audio Player)を扱う。時期は1997年〜1998年である。 ワイヤレス電力伝送で実際に電子機器を動作させる
ワイヤレス電力伝送で実際に電子機器を動作させる
今回は「7.4 試作例」の講演パートを解説する。ワイヤレス受電端末を試作し、低消費電力の小型機器をワイヤレス電力伝送で動かした。 ワイヤレス受電用端末の試作に向けたアンテナの設計作業
ワイヤレス受電用端末の試作に向けたアンテナの設計作業
今回は「7.2 アンテナ」と「7.3 アンテナの集積化」の内容について、簡単に解説する。 ワイヤレス電力伝送の過去から未来までを展望
ワイヤレス電力伝送の過去から未来までを展望
今回から、「IEDM 2021」でオランダimec Holst Centreでシニアリサーチャー、オランダEindhoven University of TechnologyでフルプロフェッサーをつとめるHubregt J. Visser氏が講演した「Practical Implementation of Wireless Power Transfer(ワイヤレス電力伝送の実用的な実装)」の内容を紹介する。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
- 中国がEUV試作機 世界の半導体市場は完全に分断されるのか
- DDR5の異常な価格急騰はなぜ起きた? 推測できるシナリオは
- 高品質・低価格のモノシリコン育成に成功
- ローム、小型薄型IoT機器向けBMS評価ボード開発
- Rapidus、千歳で製造した2nm GAAトランジスタの試作品を初展示
- 25年Q3のファウンドリー市場は848億ドルに 在庫調整終了の兆しも
- 日清紡マイクロデバイスが早期退職を募集 対象は45歳以上社員の約20%
- 「ガラスの弱点」克服するコア基板 FICTが展示
- AIにこそ「汎用プロセッサ」を 米新興が省エネチップを開発
- 25年2Qの半導体企業ランキング、日本勢トップは13位のソニー