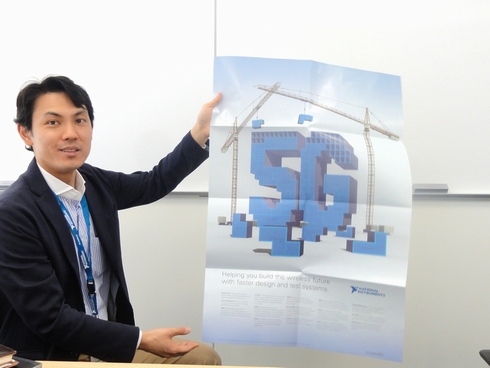ワイヤレス/RF市場のパラダイムシフトを支えるNI:“後発”だけど狙うは“最先端”
ナショナルインスルメンツ(NI)は、5年ほど前にワイヤレス/RF市場向け計測/試験装置分野に本格参入した。参入当時から大規模MIMOなど多くの革新的技術を必要とする第5世代携帯電話通信方式(5G)など次世代技術に向けた製品、サービスの展開に特化し、それら最先端技術の開発現場での採用実績を増やしている。
ナショナルインスツルメンツ(以下、NI)は、およそ5年前にワイヤレス/RF分野に参入した。計測/試験装置の最大用途市場で多くの計測機器ベンダーが凌ぎを削るワイヤレス/RF市場で、NIのワイヤレス/RF分野での歴史はとても浅いといえるだろう。
ワイヤレス/RF分野では“最後発”といえるNIだが、NIがワイヤレス/RF関連ビジネスで見据えているのは“最先端”だ。
NIが参入した5年前は、ちょうどLTEの商用サービス開始を間近に控えた時期で、計測機器市場もLTE、第4世代携帯電話通信方式(4G)向けのビジネスが盛り上がりつつあった時期だ。しかし、NIは参入当初から、第5世代携帯電話通信方式(5G)を見据えた投資を展開してきたという。5Gは、2020年ごろの商用サービスが予定され、まだ標準化されてない、現時点でもまだまだ“将来の技術”だ。
競争の激しいワイヤレス/RF分野にNIが参入した理由は、この将来の技術である5Gが密接に関係している。5GのためにNIはワイヤレス/RF分野に参入したともいえるのだ。
5Gは先に述べたようにまだ標準化されておらずどのような通信技術が用いられるか決まっていない。ただ、通信速度10Gビット/秒以上で大容量の通信方式となるよう技術の開発、選定が行われている。
ワイヤレス/RF市場参入の狙い
通信速度10Gビット/秒は、4GのLTEに比べおおよそ100倍であり、通信容量もLTEの1000倍になるとされ、大幅な性能向上をもたらす技術革新が必要だ。3GからLTEなど4Gへの進化する場合にも多くの技術革新が実現されたが、4Gから5Gへはそれ以上の大きな技術革新が必要だとされる。
分かりやすい例が、複数のアンテナで通信行うMIMO(Multiple Input Multiple Output)だ。MIMOは既にLTEでも2×2 MIMOや4×4 MIMOといったアンテナ2本、4本の構成が用いられ、LTEの後継規格で「4.5G」とも称されるLTE-Advancedでは8×8 MIMOの8本構成だ。これが5Gになると128×128 MIMOになるという。LTE-Advancedと比べても、2桁も多い100本以上のアンテナで同時に通信を行う訳であり、5Gを実現するための技術的なハードルの高さがうかがえる。MIMO以外にもLTEやLTE-Advancedよりも高い周波数帯、広い周波数帯への対応といった高度な技術課題が幾つも存在する。
こうしたパラダイムシフトとも呼べる大きな技術革新が必要な5Gの開発には、計測/試験装置も大きな技術革新が迫られている。MIMOの各アンテナの信号測定は通常、アンテナ1〜2本に対し1台の計測器を要する。8×8 MIMOであれば、4〜8台のスペクトラムアナライザを並べ同期して信号を測定する。だが、5Gの128×128 MIMOになれば、これまでのスペクトラムアナライザを使った測定手法が通用しないことは火を見るより明らか。100台以上の装置を購入するコスト、100台以上の装置を並べるスペースなどいろいろな部分で無理がある。
従来技術が通用しない領域
「これまでと異なる計測/試験技術が必要」(日本ナショナルインスツルメンツ テクニカルマーケティングマネージャ 久保法晴氏)という5Gに、NIはビジネス機会を見いだし、5Gをはじめとした新たな通信技術に焦点を絞ってワイヤレス/RF市場に参入したのだ。
参入から5年、狙い通りに5Gの実用化に向けた最先端の技術開発現場でNI製品の活用が始まっている。例えば、128×128 MIMOのような大規模MIMOのプロトタイプ開発だ。
大規模MIMOの理論を実証するには当然、プロトタイプのハードウェアが要るが、容易ではない。繰り返しになるが、100本以上のアンテナに相当する信号発生器などの計測/試験装置を動かすことは難しく、理論実証のために専用ハードを何度も制作することは不可能だ。そうした大規模MIMOの理論実証の現場で、使用されているのが、モジュール式計測器「PXI」と、ソフトウェア無線プラットフォーム「NI USRP」、そしてグラフィカル開発ツール「LabVIEW」だ。
その1つPXIは、PCI Expressに、同期を強化したNI独自の高速インタフェース「PXI Express」で、RF信号アナライザやRF信号発生器などさまざまな計測モジュールを搭載できるプラットフォーム。モジュールの追加も容易で、何百チャンネルものデータを計測、収録する用途に向いており、128本のアンテナから成る大規模MIMOシステムのプロトタイプを10個のシャーシで実現可能だ。
NI USRPは、変調/復調アルゴリズムなど物理層アルゴリズムをハードウェア環境に落とし込むためのデバイス。PXIとNI USRPは、GUIベースの開発ツールであるLabVIEWでプログラムでき、これら3つのNI製品を利用することで、大規模MIMOでの通信アルゴリズムのテストが行えるのだ。
5G向けの通信技術開発者として著名な米ニューヨーク大学のTed Rappaport博士は、PXIとNI USRP、LabVIEWに、アップ/ダウンコンバータなどを組み合わせ、ニューヨーク市街で、60GHzや72GHzという高周波数帯域を使った空気伝搬による通信の実証実験を成功させているという。また同様に、独・ドレスデン大学やスウェーデン・ルンド大学といった5G向け技術研究で著名な大学でこれらNI製品の活用がされている。
新技術求めるパワーアンプへも
NIがターゲットにするワイヤレス/RF分野の最先端領域は5G以外にもある。携帯通信端末に搭載されるパワーアンプ(PA)のテスト分野だ。PAは、端末から基地局へ信号を送るため信号を増幅するデバイスであり、通信端末のデバイスの中でも多くの電力を消費するデバイスの1つだ。そのため、PAの消費電力を下げる技術開発が盛んで、最近では、「エンベロープトラッキング」(ET)という技術のPAへの導入が進んでいる。PAはこれまで、増幅の大きさにかかわらず、PAが最も大きな増幅を行うために必要な電力が一定に供給されてきた。PAは、基地局と端末の距離などに応じて増幅率を変えるため、小さな増幅を行う場合には無駄な電力を消費することになっていた。これに対しETは、増幅の大きさに応じた最小限の電力を供給するため、供給電圧を可変する技術だ。これにより無駄な電力消費が抑えられる。しかし、PAは電力的な余裕が小さい場合、増幅した信号に歪みが生じるという欠点がある。そこでETでは、電力供給を最適化すると同時に「逆歪み」をPAに与えて、歪みを打ち消し信号品質を保っている。
このETを採用したPAのテストは困難だ。PAに任意の信号を与える信号発生器と、PAの出力を計測するスペクトラムアナライザを高度に同期する必要がある。また、LTE-AdvancedやIEEE802.11ac(以下、11ac)など最新無線規格は160MHzの広帯域で通信を行うため、広帯域対応が欠かせない。さらに、信号とともに、電源とも高度な同期を図る必要がある。
こうした用途にも、1つのシャーシで、信号発生器、アナライザなどのモジュールを高速インタフェースで接続、同期できるPXIが有効だ。NIでは、PAのテスト用途などに向けて、PXIベースのベクトル信号トランシーバを製品化。65MHz〜6GHzの周波数範囲で、最大200MHzの帯域幅に対応でき、LTE/LTE-Advancedや11acの周波数帯域をカバーし、1台のベクトル信号トランシーバで効率的にPAの特性評価が行える。PAの大手メーカーであるトライクイントセミコンダクターやWi-Fi用チップセットベンダーであるクアルコムアセロスなどで採用され、PAの特性評価時間を従来比10〜200倍速めたという結果も生まれているという。
NIでは、今後も、これまでの計測/テスト手法と異なる新たな手法を求めるワイヤレス/RF分野の“最先端領域”に着目した技術/製品の提供を行っていく方針だ。
関連キーワード
MIMO(Multiple Input Multiple Output) | 通信 | LTE(Long Term Evolution) | 参入 | 電力 | アンテナ | 改革 | 周波数 | LTE Advanced | 信号発生器 | テスト | 試験 | 検査機器 | モバイル通信 | モバイルネットワーク | パラダイム | ソフトウェア | 大学 | ベンダー | アルゴリズム | LabVIEW | ナショナルインスツルメンツ | プラットフォーム | プロトタイプ | スペクトラムアナライザ | 技術開発 | 無線 | 第5世代移動通信(5G) | 基地局 | 第4世代移動通信(4G) | チップセット | 通信規格 | 実証実験 | 消費電力 | IEEE802.11ac | 新技術 | 次世代 | 最適化 | PCI Express
関連記事
 “ソフトで設計できる”モジュール式計測器、数百チャンネルのデータもナノ秒レベルで同期
“ソフトで設計できる”モジュール式計測器、数百チャンネルのデータもナノ秒レベルで同期
日本ナショナルインスツルメンツ(日本NI)の「PXI」は、ソフトウェアでさまざまな機能を追加できるハイエンド向けの計測器だ。モジュールを必要なだけ付け足していくタイプの計測器で、数チャンネルの小さな計測システムから、数百チャンネルという巨大なシステムまで柔軟に構築できる。 社会人/大学生に交じって遠隔制御ロボットで受賞! “C言語が苦手な中学生”に聞く
社会人/大学生に交じって遠隔制御ロボットで受賞! “C言語が苦手な中学生”に聞く
日本ナショナルインスツルメンツ(日本NI)は、NI製品を使ったアプリケーションを表彰する「グラフィカルシステム開発コンテスト2013」を実施し、「未来のエンジニア賞」として、中学3年生の野口宙さんを表彰した。中学3年生ながら、NI製品を使いこなし、誰でも操作可能な遠隔制御ロボットを製作した野口さんにインタビューした。 ポケットにFPGA搭載の計測器を、学生実験を一新するアプローチ
ポケットにFPGA搭載の計測器を、学生実験を一新するアプローチ
実験室にこもり、基板や箱型計測器とともにひたすら実験を繰り返す――。こんな学生実験のスタイルが大きく変わるかもしれない。デュアルコアのCortex-A9とFPGAを1チップ化した「Zynq」を搭載した、文庫本サイズの計測/制御機器が登場したのだ。ひらめきが訪れたら、学食でもカフェでもさっと取り出して実験することができるようになる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング
- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ
- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」
- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化
- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす
- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望
- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加
- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点
- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由
- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増
- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

 日本ナショナルインスツルメンツ テクニカルマーケティングマネージャ 久保法晴氏
日本ナショナルインスツルメンツ テクニカルマーケティングマネージャ 久保法晴氏 ソフトウェア無線プラットフォーム「NI USRP」
ソフトウェア無線プラットフォーム「NI USRP」